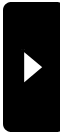「向日葵の丘」が公開されたら、観に行こう!と思っている方へのお願い。

「わーい! 私の街でも『向日葵の丘』の上映が決まったぞー。公開されたら観に行こう〜」そう思っている、あなた。何か忘れていませんか?
そう。映画はどのくらいの期間上映していると考えていますか? 「え、普通、映画は2−3ヶ月はやってんじゃないの? 時間があるときに観るつもりだけど」と思ったら大間違い。
2−3ヶ月も上映するのは大手映画会社が関与した作品のみ。通常の映画は客が来ないとすぐに打ち切り。それが映画館のシステム。それどころか、公開前に売り出される前売り券。これが売れないと上映がスタートする前に、「1週間で終了」とか決められてしまう。
つまり「前売り券が***枚売れた。これだけ売れればその*倍は客が来るから2週間は上映しよう」とかいうふうに映画館は上映期間を決める。もし、枚数が出ないと、「これは客は来ないなあ」と考えて1週間ということがあり得る。
さらに「1日何回上映されるか?」も前売り券の売れ行き次第。あまり売れないと、1日1回上映。それも早朝1回ということもある。客が来そうにない映画は早めに対応。儲かる映画を優先。それが映画館の経営なのだ。
が、その辺を知らない人が多い。どんな映画でも2−3ヶ月上映され、1日に3−4回上映されると思い込んでいる。だから、映画が公開されたら、その内に観に行こうと考える。

そうやって日曜日に映画館に行ったら、もう朝の回の終了! 次は明日。来週の日曜日には上映は終わっている。「えーーー楽しみにしていたのに何?」となり、「もっと長く、上映してほしかった!」とネットでコメントしても、もやは遅し!それが映画興行なのだ。
では、どうすればいいのか? 多くの人が前売り券を買うこと。そうすれば映画館は「おー、これは客が来るな。***枚売れたということは、その2、3倍の客が来るはず。それなら1日3回、4週間は上映しないと!」と考える。となると、日曜は4回。午後から行っても映画を観ることができる。
今回の「向日葵の丘」多くの人が応援してくれている。「必ず観ます」といってくれる人が多い。でも、その多くが、先に説明した映画館事情を知らない。ほとんどが前売り券を買わず、当日券で行けばいいと思っている。そうなると、映画館行ったけど、1日1回上映。或は、もう上映は終わっていた....ということが多発するはずだ。
「だから、前売り券を買ってほしい!そうすれば映画館は長期間上映してくれる」とこの数週間、何度もお願いした。多くがチケット買ってくれれば、上映期間や上映回数が増えるだけでなく、上映する映画館の数も増える。東京や大阪に観に行かなくても、横浜や奈良でも観ることができるだろう。
残念ながら現段階では、そんな事情を知らない人がもの凄く多く、特に大阪地区は苦戦している。そして、他の地区だって、十分ではない。前売り券を買えば当日券より500円も安いし、三大都市の映画館で買えばポスターももらえる。そして、映画上映期間が延びる。ぜひ、協力してほしい。
(前売り券ー発売している映画館)
品川プリンスシネマ
東京都港区高輪4ー10ー30
TEL 03ー5421ー1113
渋谷シネパレス
東京都渋谷区宇田川町20ー11
TEL 03ー3461ー3534
梅田シネリーブル
大阪市北区大淀中1ー1ー88
TEL 06ー6440ー5930
布施ラインシネマ
東大阪市足代新町7ー4
TEL 06ー6782ー2628
伏見ミリオン座
名古屋市中区栄1ー4ー16
TEL 052ー212ー2437

2015年06月11日 Posted by クロエ at 07:19 │Comments(0) │MyOption
「向日葵の丘」現代の映画の役割。娯楽だけではなく、大切なことを伝えること。

1980年代。映画は現実逃避の手段でした。辛い世の中。2時間の間、現実を離れ宇宙を旅し、悪い奴らをやっつけて、イケメン男性や美女と恋をする。ハラハラ、どきどき、笑って、泣いて、感動する。そして映画館を出れば、現実に戻り、また「明日もがんばろう」と思うための応援メディアとしての役割が大きかった。
その後、90年代に入り、バブル崩壊。不況が10年以上も続く。2010年代に入ると、311。原発問題、景気問題、法改正、集団的自衛権等、テレビや新聞は本当ことを伝えず、戦争の足音さえ聞こえてくる。時代は悪い方向に進んでいるように思えてる。未来が見えない。希望が感じられない。そんな時代の中で映画の役割も変わってきたと思える。
80年代は「辛い!」と思っても、どうにか生活はできた。まじめに勉強して、会社に入り、しっかり仕事をすれば家族は守れた。だから、仕事が辛い、生活が苦しいといっても2時間映画で現実逃避すれば、また、がんばろうと思えたのだ。が、今は違う。2時間の現実逃避では何も解決しない。
豊かだったはずの日本で餓死する人がいる。信じていた会社が倒産。仕事をなくしてしまう。それ以前に就職できない。正社員になれない。ブラックな会社では過労死するまで働かされる。そんな時代に2時間の現実逃避をさせるだけの映画に意味を見いだしてはもらえない。
今の時代。映画は何を描くべきなのか? 僕がデビュー作「ストロベリーフィールズ」から描いて来たのは「親子に伝える大切なこと」。忘れがちな大切なことを物語を通してもう1度見つめることがテーマだった。そして、ここ最近はさらに、一歩進めて「幸せとは何か?」を考える。
日本人にとって、親にとって、子供にとって、家族にとって、一番大切なことは何か? 何が人を幸せだと感じさせるのか? 幸せって何だっけ? そんなことをテーマに、ハラハラ、どきどき、感動して泣ける映画を作っている。
今回の舞台は1983年。あの時代を振り返ることで、見つめることで、思い出すことで、忘れていた大切なことに気づくはずだ。パソコンもない、DVDもない、CDも、携帯さえもない時代。そんな時代にあって、今は失われたもの。それこそが「幸せ」なのだと思える。では、それは何か?
でも、説教臭い物語ではない。今回もめっちゃ泣ける作品になっている。ラスト1時間は、今回も涙の連続だ。その涙の中で、その感動の中で、あなたもきっと忘れていた大切なことを見つけるはずだ。
「向日葵の丘」は8月22日から東京、品川プリンスシネマで公開。つづいて9月12日からは渋谷シネパレスで公開。東京がヒットすれば、大阪、名古屋公開も可能性が出てくる。応援頂けるとうれしい。

2015年06月09日 Posted by クロエ at 05:40 │Comments(0) │MyOption
「向日葵の丘」は参加者全員の映画。映画館で感動を分かち合ってほしい。そのために必要なこととは?

僕はセリフのない役の一般出演者をエキストラとは呼ばない。「エキストラ」というのは、「その他」という意味。映画は皆が主人公。通行人役だろうと、セリフがない役だろうと、1人1人が主人公。だから、太田組では「市民俳優」と呼ぶ。
今回も一般オーディションを行い、多くの人が参加。結果的に1000人近くに出ていただいた。セリフがある重要な役から見物人役まで、でも、全員が主人公だ。ご存知の方も多いが、僕の映画の登場人物は全員が主人公。人生に端役と主役なんてないように、ドラマだって本来は全員が主人公なのだ。
映画に参加してくれた人たちも同じだ。セリフのある役。ない役。スタッフのお手伝いをしてくれた方。機材運びを手伝ってくれた方。セットの掃除をしてくれた方。小道具を貸してくれた方。差し入れをくれた方。みんなみんな、映画作りの一端を担ってくれた存在であり。皆が映画作りの主人公だ。

そんな参加者は、映画が公開されたとき「あそこ映っているのは私!」「あの小道具、貸したのは俺」「この日の撮影に差し入れした!」「友達の***さんが出ている」と様々な形で楽しんでもらえる。これは観客ではなく、参加した人だからこその楽しさ。映画館で上映して、多くの人に見てもらって一緒に感動すれば、もっと嬉しい。
そのために大切なのは宣伝なのだが、ここに来て多くの関係者、僕のFacebookには多くの「いいね」をくれるが、映画の宣伝をしてくれている人は少ない。前売り券を買ってくれたのは、極々わずか。「応援します」「必ず見ます」という人はFacebook上でも千人はいるのに、チケットを買ってくれたのは全国で数十人しかいない。
買ってくれたからと僕には1円も入らない。宣伝してもギャラはもらえない。でも、前売り券がたくさん売れれば、映画館が長く上映してくれる。地方の映画館も上映したい!といってくる。そうすれば、応援してくれる人が映画を観やすくなる。関心のない人も観るチャンスが増える。だから、前売り券を売らねばならないのだ。

しかし、テレビ局がバンバン宣伝してくれない。チケットを買ってもらうのは容易ではない。それ以前に映画の存在を知らない人が、何万人もいるのだ。だから、僕はFacebook、ブログ、Twitterで情報を1日に何度も発信している。あちこちで宣伝活動をしている。なのに「応援します」「必ず見に行きます」という多くの人がただただ「いいね」を押して公開を待っているのが現状。
あの日の努力を、撮影のときの大変さを、カメラの前に立ったときのドキドキを、仲間と共に感動し、喜べるのが映画館公開。その喜びを、友達や家族と分かち合ってほしい。そのためにも、映画館で長く上映してもらい、日本各地の映画館で上映してもらわねばならない。そのためには前売り券が売れることが一番重要なんだ。でも、僕が一人で宣伝しているだけではダメ。
店にポスターを貼ってほしい。チラシを配ってほしい。ネットで映画のことを書いてほしい。みんなでチケットを買い、あるいは売ってほしい。「向日葵の丘」はみんなの映画。あなたたちの、私たちの作品。あなたが何もしなければ、映画の上映はすぐに打ち切り。がんばれば、全国で上映。多くの人が見ることができる。行動することで感動を伝えられるはずだ。

2015年06月04日 Posted by クロエ at 14:14 │Comments(0) │MyOption
「向日葵の丘」は参加者全員の映画。あなたの物語。行動してほしい!

映画は1人では作れない。監督1人では何もできない。キャストがいて、スタッフがいて、ロケ地の応援があり、応援団の助けがあり。関係者の援助があって初めて完成する。
「映画は監督のもの」といわれるように、作品の出来は監督の責任。でも、映画自体は参加者全員のものだ。だから、僕はセリフのない役の一般出演者をエキストラとは呼ばない。「エキストラ」というのは、「その他」という意味。映画は皆が主人公。通行人役だろうと、セリフがない役だろうと、1人1人が主人公。だから、太田組では「市民俳優」と呼ぶ。

今回も一般オーディションを行い、多くの人が参加。結果的に1000人近くに出ていただいた。セリフがある重要な役から見物人役まで、でも、全員が主人公だ。ご存知の方も多いが、僕の映画の登場人物は全員が主人公。人生に端役と主役なんてないように、ドラマだって本来は全員が主人公なのだ。
誰にも人生があり、そのドラマの中では、誰もが主人公。だから、映画でも皆が主人公と考える。その1人と別の1人の人生が交差した、その瞬間。そこに物語が生まれる。それが映画だと僕は考える。
映画に参加してくれた人たちも同じだ。セリフのある役。ない役。スタッフのお手伝いをしてくれた方。機材運びを手伝ってくれた方。セットの掃除をしてくれた方。小道具を貸してくれた方。差し入れをくれた方。みんなみんな、映画作りの一端を担ってくれた存在であり。皆が映画作りの主人公だ。

そんな参加者は、映画が公開されたとき「あそこ映っているのは私!」と一般のお客とは違う形でも喜んでもらえる。「あの小道具、貸したのは俺」「この日の撮影に差し入れした!」「撮影で使ったこの店、私が紹介した!」「友達の***さんが出ている」と様々な形で楽しんでもらえる。これは観客ではなく、参加した人だからこその楽しさ。
1人1人の力が結集したからこそ、映画は完成できた。あなた方1人1人の努力の成果なのだ。だが、映画は作るだけではダメ。上映して、多くの人に見てもらってこそ映画になる。参加者以外の多くの人たちにも見てもらい「感動」を伝えてこそ意味がある。内輪だけで見ていては意味がない。
そのために大切なのは宣伝。「こんな映画があるんだぞー」と伝えること。そして、前売り券。多くの枚数が売れれば、映画館は関心を持ち「ぜひ、うちでも!」と手を挙げる。「こんなに売れたのなら、3ヶ月は上映しないとな〜」と支配人は考える。
だが、ここに来て多くの関係者、参加者が、他人事になっている。僕のFacebookには多くの「いいね」をくれるが、映画の宣伝をしてくれている人は少ない。前売り券を買ってくれたのは、極々わずか。皆、いつしか、お客様になっていて「映画、早くみたいな〜」と待っているだけではないか?

僕の映画は大手映画会社やテレビ局が作るメジャー映画ではない。テレビ局がバンバン宣伝してくれることはない。だが、多くの「思い」がある方々の力を借りて作ったので、素敵な映画ができた。企業映画では絶対にできない感動作になった。なのに多くの人がただ「いいね」を押して公開を待っているだけ。
あの日の努力を、撮影のときの大変さを、カメラの前に立ったときのドキドキを、仲間と共に参加したあの日々を物語に変えて、全国に伝えるのが映画館公開。その感動を伝えてほしい。伝えなければ多くの人に映画を見てもらうことはできない。いくら待ってもテレビで宣伝はしてくれない。
店にポスターを貼ってほしい。チラシを配ってほしい。ネットで映画のことを書いてほしい。チケットを買い、売って、映画館で1日でも長く上映してもらい、1館でも多くの劇場で上映できる応援をしてほしい。僕が一人で宣伝してもダメなんだ。
「向日葵の丘」はみんなの映画。あなたたちの、私たちの作品。あなたが何もしなければ、映画の上映はすぐに打ち切り。がんばれば、全国で上映。多くの人が見ることができる。あの日の感動を一緒に伝えよう!

2015年06月03日 Posted by クロエ at 14:30 │Comments(0) │MyOption
「向日葵の丘」希望は必ずある。諦めてはいけない。
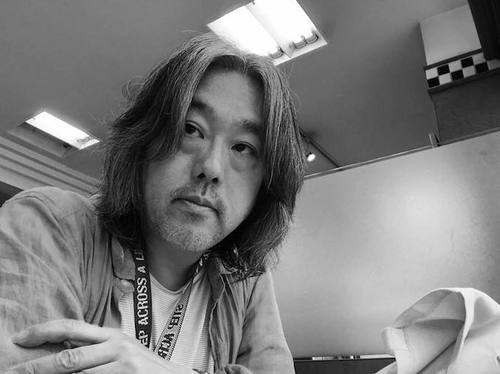
いろんなことが見えてきた。
悲しみ。絶望。落胆。失望。裏切。
でも、諦めてはいけない。
必ず希望はある。
今は見えなくても、必ずある。
絶望してはいけない。
信じれば、そこに希望がある。
それを伝える映画を作りたい。

2015年06月03日 Posted by クロエ at 09:30 │Comments(0) │MyOption
「向日葵の丘」「マネーの虎」を見て痛感したこと。商売も映画も「才能」ではない。

その番組は10年ほど前に放送されていた。吉田栄作が司会で、金持ち社長が5−6人(皆、うさん臭い!そこがまたいい)会議室に集まり、そこに応募してきた視聴者がプレゼン。その商売プランが気に入られれば、出資してもらえるという番組。
かなり過酷な番組で、虎と呼ばれる社長たちはプランを説明する若者たちに情け容赦ない質問をぶつける。質問どころか「お前は甘い」と説教する虎もいる。が、聞いていると虎たちのいうことは正論で、なるほどということが多い。プレゼンする若者たちがいかに安易で、真剣さが足りないか?痛感。そこが面白くて、深夜枠で放送していて頃から見ていた。
その頃僕は、監督デビュー作「ストロベリーフィールズ」の製作費を出してもらおうと、映画会社やビデオメーカーにプレゼンを続けていた。が、なかなか、うまく行かず、苦闘している時期だった。友人たちからは「絶対に不可能」「誰がお前みたいな無名の監督に金を出すの?」「あり得ない」「諦めた方がいい!」そう言われていた。

なので、番組に応募した人たちの気持ちがよく分かり、自分が虎たちを相手にプレゼンしているような気持ちになり、毎回「やはり、世の中は甘くないよなー」と思えて暗い気持ちになった。そんなとき、ある回でプレゼントする若者にある虎がこう訊いた。
「成功しないでいる君と、成功した僕たちと何が違うんだと思う?」
嫌な質問だが、興味あるところだ。大金持ちになった社長たちと、いろんな挑戦が失敗して行き詰まり、金を借りることもできず、テレビ番組に応募。新事業の出資を願うその若者と何が違うというのだろう。「実力」「運」「才覚」そんなありふれた言葉が僕の脳裏を過る。若者は答える。
「......努力......ですかね? 僕はまだまだ努力が足りない。でも、社長さんたちは僕の何倍も、何十倍も努力してきた。そういうことじゃないですか?」
それも言える。世の中は努力が大事というのはよく言われる。だが、海千山千でのし上がって来た社長が、そんな当たり前のことをいうだろうか? では、何か? いろいろと考えたが、分からない。すると、その社長はニヤリと笑い、こういった。
「考え方だよ」
あーーーーーーーー、なるほど。そうかーーーー。その通りだと思う。というのは、似たような話を他でも聞いたことがあり、僕も漠然と近いことを考えたからだ。つまり、その若者の事業が成功しないのは「努力」が足りないからではなく、「考え方」が間違っているからと社長は指摘するのだ。いくら努力しても「考え方」が間違っていれば成功はしない。
その若者は間違った方法論を努力した。だから、儲からなかったのだ。これは僕が日頃から言っている「才能なんてない」というのと同じ発想だ。才能があるから映画監督になれる。とか、いい映画を作れる。とよく言われるが、そうではない。と思っていた。まさに同じだ。

努力とか、才能とか、ではなく、考え方。それを間違えたら何事もうまく行かない。具体的にいうと、店をやるなら仕入れ、調理、人員、味、コスト、客層、時代の流れ、宣伝等を徹底して考えて、自分がやりたいコンセプトをどうすれば、その中で生かすことができるか? その方法論を考えることなのだ。一生懸命、努力して店で働くだけでは客は来ないし儲からない。そもそもの方法論=「考え方」が大事というの意味だ。
当時、僕も映画製作費を集めるのに、ありとあらゆる人に批判、否定され続けていた。が、「考えれば必ず答えがある」と考えていた。親が金持ちでなくても、自身が有名人でなくても、大企業に友達がいなくても、何か方法があるんじゃないか? そう考えていた時期なので、その虎がいったことは納得。同時に励まされた。
虎たちも同じ発想で成功したんだ。そう思うと元気が出た。実際、僕は1年後に目標の製作費を集め、映画監督デビューした。皆、「まぐれ」といったが、さらに2作の製作費を自身で集め、映画を作り続けてた。いえることは、「才能」とか「大手企業の力」とかがなくても、誰でも成功できるということ。夢を実現することはできるということなのだ。要は「考え方」次第。が、「マネーの虎」には後日談がある。
番組終了から10年。その後、虎たちの多くは破産。倒産を経験。行方不明の社長もいるようだ。最初の「考え方」は正解だったが、いつか「考え違い」を犯し大失敗をする日が来るということだ。人ごとではない。僕も今回で終わりということもあり得る。だから、毎回、遺作だと思ってかかる。

2015年05月29日 Posted by クロエ at 20:43 │Comments(0) │MyOption
「向日葵の丘」嫌われてこそ映画監督? 「いい人」と呼ばれる奴は駄作しか撮れない?

嫌われてこそ映画監督? 「いい人」と呼ばれる奴は駄作しか撮れない?
知り合いの製作会社にいくと、よく他の監督のうわさ話を聞く。「A監督の新作、惨敗らしいよ。この間も、客が2−3人。厳しい〜。A監督、ほんといい人なのにな。がんばってほしいよねえ」
逆にこんな話も聞く。「B監督とはもう仕事することはないなあ〜。あそこまでわがままだと付き合いきれない。もう少し、チームワークとか考えないと、誰も相手にしてくれなくなるなあ」
こう聞くと、A監督はいい人だが、新作がヒットせず苦戦しており、同情を集め、応援したいという状況。比べてB監督は身勝手で嫌われている。離れて行く人が多く、存亡の危機にある。という印象を持つだろう。が、ここで抜けている情報がある。B監督の映画はヒットしているのか?というのが分からない。

実はH監督の作品は毎回ヒットしている。比べてA監督は毎回惨敗。どういうことなのか? 何度も記事を書いて来たが、その背景に映画界的な事情があるのだ。A監督。いい人で、製作会社が「この女優で行きましょう! テレビドラマのレギュラーも決まったし」というと「じゃあ、その子で行きましょう」と従う。
が、B監督は「その子じゃ無理、シナリオのイメージと違う!」ということを聞かない。一事が万事、A監督は皆と協調し、仕事をする。B監督は全てを自分で決め、人のいうことを無視。こう書くと、「仕事なんだから、やはり協調性が大事。A監督はそれを理解しているが、B監督は常識がない」と思う人もいるだろう。
しかし、映画というのは皆の意見を取り入れて、全員が満足する形で進めるといいものができない。1人の作家がやりたいようにやったときに、名作と呼ばれる作品が生まれたりする。黒澤明だって、キューブリックだってそう。巨匠と呼ばれる監督は皆、完全主義者で我がままで、誰も止めることができない。その意味でいうと、皆のいうことに従うA監督にいい作品が作れないのも当然。
さらに、製作会社というのはご存知の通り。いかに製作費を抜き、自社の利益にするか?としか考えないところが多い。いい映画を作ろう!と思ってる社は少ない。そして、面倒なことはしたがらない。さらに、自社と癒着した芸能プロダクションの俳優をキャスティングすることで、キックバックをもらったり。いざというとき大物俳優を都合してもらうときのための恩を売りたい。というようなことばかり考えている。

なのに、監督が「この俳優はダメだ」というと、キックバックももらえないし、恩も売れない。撮影も適当にやれば、そこそこで終わるが、熱を入れてがんばられるといろいろ面倒。つまり、製作会社にとって「いい監督」というのは、自分たちの言うことを聞き、面倒なことをせず、不正や癒着に目をつぶる人たちのことなのだ。だから、「A監督はいい人だ」というのだ。
それに対してB監督が嫌われるのは、本当にいいものを作ろうとして妥協せず、無理をして、努力をするから、会社としては面倒くさい。いつも以上の労力を強いられる。自分たちのいうことを聞かない。不正や癒着ができない嫌な奴なのだ。だからこういう。
「B監督とはもう仕事することはないなあ〜。あそこまでわがままだと付き合いきれない。もう少し、チームワークとか考えないと、誰も相手にしてくれなくなるなあ」
製作会社のいう本当に意味が分かってもらえたと思う。僕も人の意見を聞かず、絶対に自分を曲げない方だから、製作会社とはよくぶつかった。一度やったところは二度と声をかけてくれなかった。プロデュサーはあちこちで悪口をいいまわっているようだ。が、まだまだ、悪評を聞くことは少ない。むしろ「太田はよくやっている」という話を聞く。これはまだまだ我がままが足りないということだ。
映画監督というのは、嫌われている人ほどいい映画を作る。「いい人だ」と言われてる人ほど、ろくでもない映画を作っている。不思議な世界ではあるが、事情を知れば「なるほどそうだな!」と思ってもらえただろう。

2015年05月28日 Posted by クロエ at 20:19 │Comments(0) │MyOption
自分の価値観を押し付ける人たち。なぜ、人はそれぞれ違うことを認めないのか?

映画撮影を終えると、お世話になった方々に挨拶まわりをする。本来、それは監督の仕事ではなく、製作担当がするのだが、僕の場合はスタッフが集まる前に、1人でロケ地に乗り込み。いろんな人を訪ね、応援を求める。そんなことを1−2年続ける。だから、本来、製作担当が行くべき挨拶まわり。僕も同行する。感謝の気持ちと無事撮影終了を伝えるためだ。ただ、スタッフから言われる。
「本来、それは製作担当がやるべきこと。監督は早く東京に戻り、編集作業を始めるべき。そして少しでも早く完成させて、応援してもらった人たちに見てもらうことこそが大事。最初は監督と出会ったことで、応援してくれた方々でも、その後、製作担当に引き継がれた仕事。それを監督が何十人もの人を何日もかけて訪ねるのはどうか? 建築業でも、ビルを建てたからと、社長が関係者を訪ね挨拶をしてまわったりはしない。それは現場担当がやるじゃないですか?」
確かに、その通りだ。が、僕は1人1人の顔も名前を知っているし、何度もごちそうになったり、いろんなことを教えてもらったりしたので、感謝の気持ちを伝えたくて、お礼参り(?)をしているのだ。が、何カ所かの地域で映画を作りをすると、あれ?と思うことも出て来た。
ある街での撮影後、いつものように地元の方と製作担当と、僕の3人でお礼参りツアーをした。その中で、あるお弁当工場を訪ねることになる。そこは大量のお弁当をもの凄く安い値段で提供してくれた。お礼を言わなければならない。

そのとき地元の方はいった。「俳優やスタッフ全員でお礼に伺いましょう。監督と製作担当さんだけでは失礼です」ん?ちょっと待ってください。弁当を扱うのは製作担当。だから、本来は彼のみが挨拶に行く。僕も本来なら行かない。が、その工場の社長とは何度かお会いしているし、感謝の気持ちを伝えたかった。なのに、地元の方はスタッフ&キャスト総出で行ってほしいという。
「俳優もスタッフも弁当を食べたんだから、お礼に行くのは当たり前だろ!」
何でそうなるのか? まず、映画の世界では、俳優&スタッフに弁当を出すのは製作サイドとして当然のこと。それが映画界の決まり。ただ、製作担当者としては、超破格の値段にしてもらえたことで、製作費を節約大助かりだった。だから、製作担当者がお礼に行く。僕も感謝を伝える。
しかし、その地元の方の考えはこうだ。何かをごちそうになったら本人がお礼をいうべきだ。という一般的な発想なのだ。確かに、地元の家に呼ばれて、夕飯をごちそうになれば、呼ばれた客はお礼をいうのが当然。
ただ、映画撮影にその構図は当てはまらない。例えるなら、農家がある社員食堂に超破格で野菜を卸した。その食堂で社員が食事をした。お礼に行くのは社員食堂の担当者だ。食事をした社員はいつもと同じにご飯を食べただけ。なのに、社員も全員、お礼に行けというのと同じになる。
そして、もし、それを実行すれば、バスをチャーターして、1日スケジュールを空けて、皆でお弁当工場に行かねばならない。宿泊費も1日分プラス。当然、俳優事務所はクレームを付ける。なぜ、うちの俳優に挨拶まわりをさせる。
弁当を出すのは製作サイドの義務。演技以外のことをさせるなら、追加ギャラを寄越せというところも出てくる。結果、全員で行くことで、せっかく破格の値段にしてもらったのに、相当の出費をせねばならない。だったら、通常の業者から弁当を買った方が安上がり。

でも、その人は映画界の事情が分からない。できれば、先の社員食堂の構図を想像してくれればいいが、スタッフもキャストも皆、撮影隊のメンバーとひとくくり。全員でお礼をいいに行ってほしいと主張する。事情を説明すると、無理であることは理解してくれた。「じゃあ、監督と製作さんだけでいいよ」といい、彼は弁当工場の社長に平謝りしていた。
挨拶まわりを全て終えて、帰京しても、あとからクレームが来ることがある。「撮影終了から1ヶ月。なぜ、挨拶に来ない。あれだけ応援したのに失礼な!」と言われたこともある。なんで1ヶ月? と思ったのだが、その人の業界では1ヶ月後にあらためてお礼をするのが習わしなのだそうだ。
だが、こちらは編集の真っ最中。その上、製作担当はすでにプロジェクトを離れて、別の仕事をしている。おまけに、別の業界のしきたりを映画作りに押しつけられても困る。こちらは撮影終了。完成。公開。を区切りに挨拶に行っているのだ。そんなふうに先方には先方の習わしがあるのだが、それを映画作りにも当てはめて、怒られたことがある。
宗教の違いで戦争をする国がある。同じ反原発を訴えながら、些細な違いで互いを批判しあう人たちがいる。推進派を攻撃するなら分かるが、反原発を主張する同士が中傷し合う。どの分野も自分の価値観を絶対だと信じ、それを押し付けようとする。方法論が違えば、自分なりのやり方で進めばいい。違う相手を否定する必要はない。自分の価値観を相手に押し付ける必要はないのだ。
このFacebookでも、自分と意見が違うと長々と批判コメントして来る人がいるが、(或はダイレクトメッセージを送ってくる)それは自分のFacebookで書けばいいこと。なぜ、人は他人に意見や価値観を押し付けるのか? そんなことをときどき考えてしまう。

2015年05月26日 Posted by クロエ at 17:44 │Comments(0) │MyOption
受験勉強をがんばって、それなりの大学、会社に進んだ友人の寂しい今?

高校時代の勉強というのは本当に役に立っているのだろうか? 数学、漢文、古典、現国、化学、日常生活で使うことはない。英語も、中学から6年も勉強しているのに、皆、話すことさえできない。あの6年間は何だったのか? あえて意味を求めるならば、それらを勉強することで、大学受験に合格し、よりよい大学に入るため。その1点に集約される思える。
そして、いい大学に入れば、いい会社に就職でき、それなりの給与をもらい、安定した生活が送れる。その意味で、日常生活に役には立たなくても、高校時代の勉強は意味あったとも言える。僕の友人も、そんなパターンで、それなりの会社に就職。サラリーマン生活をしていた。
が、バブル崩壊で会社が倒産。その後、新たな会社を探したが、いい歳なので再就職がむずかしい。そして、彼には何も技術がなかった。英語を話せる訳でもない、コンピュターが得意な訳でもない。特殊な技術も持たない。ただ、与えられた仕事をするだけのサラリーマンだった。
以前と同じような会社に就職口はなく、今は組み立て工場に仕事を見つけ、パートのおばちゃんと一緒に仕事をしている。それなりの会社で、それなりの仕事をしていただけに、不満があるようだ。「何で大学出の俺がこんな作業をせねばならない」でも、真面目な彼は仕事を続けている。
高校時代から僕は「こんな勉強をして何になる?」と思っていた。友人は「俺もそう思うけど、仕方ないだろ?」と答えていた。けど、僕は「無意味だ。意味がない。もっと将来役立つことを勉強すべきではないか? しゃべれる英語をなんで教えてくれない!」別の級友が答えた。「そんなに勉強が嫌だったら、学校を辞めて自分なりに好きな勉強をしろよ!」
僕は訊いた。「なんで、学校で役に立つ勉強をしない? それを指摘しているんだ。お前は毎日の授業が将来、役に立つと思っているのか?」級友は答える。「そんなこと知らねえよ。嫌なら辞めればいいんだ!」そんなふうに多くの級友は、「なぜ、勉強するか?」の意味は考えず。与えられることを疑わずに、毎日勉強していた。
けど、僕は当時からひねくれ者で、高校の3年間は本当に無意味な時間だと感じた。屈辱と絶望の日々。暗黒の時代だった。なぜ、10代の記憶力のいい、頭が柔らかい内に、将来役に立つことを学ぶことができないのか?憤りを感じていた。
勉強する意味が感じられず。映画を観たり、本を読んだり、レコードを聴いたり、漫画を書き、8ミリカメラをまわしたり。好きなことしかしなかった。そして大学進学を拒否した。ま、その後、アメリカの大学では勉強するのだが。友人たちは皆、それなりの有名大学に進学。その後、いろんな企業に就職する。
僕は当時の級友から「負け組」といわれ、帰国してからも就職しないでいると「いつまでフラフラしているの?」「まだ、映画なんかやってるのか?」と言われた。直後、バブルが崩壊。友人の何人かは失業した。
それから20年ほど。僕は今、高校時代に勉強せずにやっていたことが仕事で生きている。小説をたくさん読んだこと、レコードを聴いたこと、8ミリカメラをまわしたからデジカメはまわせる、漫画も書いていたからコンテも描ける。映画を作る上で必要なことを実は当時全部やっていた。今も決して、裕福な生活はしていないが、好きな仕事を続けている。自慢話ではない。僕自身、こうなるとは思ってなかったのだ。
会社が倒産した友人はいう。「俺の方がずっと成績がよかったのに、何だか皮肉な展開だよな?」本当にそうだ。そんな友人も実は夢があった。本当は作家になりたかったのだ。でも、「世の中、甘くない。作家は食えないし、安定していない」と勉強を続け、それなりの大学に合格した。そして、就職。倒産。今の彼がある。「こうなるのが分かっていたら、作家を諦めずに、がんばればよかった....」
僕の映画は「親子に伝える大切なこと」がテーマ。ときどき、親たちから質問をされる。「今、子供たちのために親は何をするべきと思いますか?」そんなときは、こう答える。「子供が一番、興味があり、好きなことをやらせてあげるべきです。
それが安定した仕事になるか?給料がどこのくらいか?は関係なく。本当に好きなことをやらせてください。それは必ず、将来、子供たちの力になります」僕は自身の経験からそう伝える。

2015年05月25日 Posted by クロエ at 06:55 │Comments(0) │MyOption
「友達」という言葉で全てを許す人たち? でも、大事な夢を実現するための「仲間」こそが大切。

「監督は女優さんなんかと、よく飲み会するんでしょう? いいなあ」なんてよく言われるが、そんなことはまずない。俳優とは基本、一線を引き、プライベートではなるべく会わないようにしている。連絡もまず取らない。キャストだけではなく、スタッフとも距離を置く。撮影前は打ち合わせで何度も会うが、用もないのに、飲みに誘ったりはしない。
なぜか? それは「友達」と「仲間」の線を引くため。「友達」というと、とてもいい響きがあり、かけがえのない大切な存在と思いがち。確かにその通りであり、僕は何度も友達に助けられた。が、同時に「友達」という美名の元に勘違いした人たちが、夢破れて消えて行った姿も見てきた。少し長いがそんな話をする。
学生時代。自主映画というのをやっていた。友達を集め、8ミリフィルムを使い、映画を作る。大学の映研のような活動。僕もそんな1人、友達を集めて映画撮影していたが、なかなか大変だった。「将来、プロになる!」と断言する連中と映画を作る。
例えば午前8時に代官山駅集合。ロケバスはないので、歩きでロケ場所の公園まで行き撮影する。が、必ず遅れてくるものがいる。5分、10分なら分かるが、1時間、2時間遅刻する者。当時は携帯電話もない。
なのに、必ず遅刻して来る奴がいる。時間がもったいないので、置いて行こうとすると、こう言う奴がいる。「可哀想だよ。待ってやろうよ」すでに30分待っている。撮影時間を30分失った訳だが、彼は「待とう!」という。が、待つことで、どれだけ多くのものを失うかが実感できていない。
撮影ができるのは夕方まで、だから、朝早くに集合して撮影。もし、撮り残しが出たら、もう一度、その公園に来て続きを撮らねばならない。そうなると、撮影終了が1日遅れる。交通費も食費も自腹だ。皆、それを負担せねばならない。その日だけ。という約束でバイトを休んで来てもらった友人もいる。その人にも、頼み込み、もう一日来てもらわねばならない。

実際、そうなったことがあったが、遅刻した者を庇った友人は、遅刻した者を責めることはなく「日が暮れたんだから仕方ない」ということが多い。これがプロデビューを目指している訳ではない、お手伝いに来た大学生がいうなら分かる。或はサークル活動ならいいだろう。けど、プロの映画監督を目指して映画作りをしている友人たちが、これでいいのか?
おかしいのは「プロの映画監督を目指している!」という同じ夢があることで知り合い、親しくなった友達同士なのだ。なのに、その夢を追うための足を引っ張る友人を庇うのはどういうことか? 僕は思う。映画監督への夢を共に目指す友達なら、その夢のために助け合い、励まし合うものであり、トラブルを起こしたり、撮影の邪魔をしてしまったことを庇い許し合うべきではない。
だから、その手の友人はメンバーから外した。しかし、友人たちは外された者に同情、その後も付き合いを続け、やがて、飲み会にも僕だけ声がかからなくなった。僕を外して彼らは映画作りを続けたか?というと、そんなことはなく。1人。また1人と夢破れ、東京を去って行った。
その後、彼らは連絡を取り合うこともなく、バラバラになったという。そんな友人たちの背景を考えると、いろんなことが見えてきた。もともと彼らははみ出し者。クラスで友達も少なく、勉強もできず、映画が好きなだけで、家族にも疎まれていた高校生だった。
それが「映画監督になろう!」と東京に出て来て、同じようなタイプの存在と出会った。共感し、仲良くなる。友達がいなかった彼らは嬉しかった。それゆえ、撮影に遅れて来ても、トラブルを起こしても、責めるより庇ってしまった。つまり、あまりに寂しい高校時代を送ってきたので「友達」に対する強い思いを抱いていた。プロデビューも嘘ではないが、今目の前にいる友達を優先したのだろう。

しかし、結果は傷ついた者同士が、傷を嘗め合う形となり。共に夢に向かって励まし合うという形にはならなかった。そして、夢破れて消えて行った。彼らは本当に友達思いだった。が、「友達」という意味をはき違えたていた。だから、僕はキャストやスタッフとも一線を引く。そして彼らは「友達」というより「仲間」だと考える。感動的な映画を一緒に作るための「仲間」。友達ありきで考えると、自主映画時代の悲劇を繰り返すからだ。
例えば、親しい俳優がいて、「友達」だったとする。そいつは頑張り屋だが、なかなか映画出演がない。それを「友達」として応援し出演させる。でも、やはり芝居がうまくない。そのために映画のクオリティが下がる。どんなに親しい「友達」でも、それは監督してやってはいけないこと。
或は大きな失態をした俳優を「友達」だからと、また出演させてはいけない。カタギの友人はいう「可哀想だろう? もう一度チャンスをやれよ。友達だろ?」そう言われたこともあるが、自主映画時代の友人を思い出す。「友達」だからと庇ってはいけない。結果、いろんな人に迷惑をかけ、互いに辛い思いをする。その映画が崩壊することだってある。それで誰が喜ぶというのか? 大切なのは友人を助けることではなく、素晴らしい映画を作ること。
そんな訳で、僕は一線を引く。互いのことを深く知ると、どうしても甘えが出る。同情する。そして、相手に罪があっても許そうと思える。「監督は私のことを分かってくれているから、許してくれるはず」という甘えがでる。僕も「こいつのために何とかしてやりたい」と思う。本来それは「友情」と呼ばれるものだが、諸刃の件。映画作りではマイナス。だから距離を置く。
自分にとって本当に大事なのは何か? 「感動してもらえる素敵な映画を作ることか?」だ。「仕事に影響しても、友達を庇うこと」ではない。大切なのは「仲間」と素晴らしい作品を作ること。その「仲間」というのは手を抜いたり、作品を阻害することを許し合う存在ではなく、同じ夢や目的を持ち、助け合う存在。そんなふうに考えている。