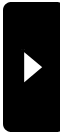「向日葵の丘」困った、、、仕事ができない
向日葵の丘ー監督日記 真夜中に目が覚めて、仕事をしてみる。

日曜というのに、昨日も朝から仕事。夜遅くに終わって、疲れ果てたままワイン飲んで寝たのに、こんな時間に目が覚める。酒飲むにも胃が痛く、仕方ないので明日やる予定だった仕事をする。現在、書き出し中。それが終わり、次の書き出しをスタートして寝れば、明日の朝、いや、今日の朝には上がっているはず。
この数ヶ月、午前中から起きて仕事をしていたので、こんな時間に起きているのは珍しい。が、本来、この時間が一番、頭も働き、集中力も高くていいのだが、健康を考えると、いつまでも夜型の生活をしているのもヤバいと思え、このところは午前中に起床。
それでなくても、「朝日」をスタートさせた2012年1月から休んでいない。昨日も日曜だが仕事。というより、土日、祭日に休んだことがない。もう、2年と9ヶ月や休みなしなので、そろそろ、また過労で倒れるのではないか?と心配。せめて、早寝早起きすることで対処しているが、意味あるかどうか?不明。
字幕スーパー原稿の確認は何とか終わったので、次はアフレコ、モノローグ第二弾、劇中CMのための台本書き。そして、メイキング素材の確認。スチール選び、そして、予告編。タイトル字の件も進めなければ。やはり、まだ倒れられない。

2014年09月29日 Posted by クロエ at 11:36 │Comments(0) │ポストプロダクション
向日葵の丘ー監督日記 何だかんだで、毎回、海外で上映される?

僕の初監督作「ストロベリーフィールズ」はカンヌ映画祭のフィルムマーケットで上映。二作目の「青い青い空」はロサンゼルスのジャパン・フィルム・フェスティバル。そして「朝日のあたる家」に至っては、ロサンゼルス、アリゾナ、シンガポール、ドイツで上映。さらにバンクーバとニュージーランドで上映が計画されている。
いずれの国でも好評。日本での上映時と同じシーンで、観客は笑い、泣き、拍手が起こった。映画監督を目指していたから、海外でも通用する映画作りが目標だったので、本当に嬉しい瞬間だった。というのも、アメリカで通用する日本映画というのは数少ないのだ。言葉の問題や製作費の問題ではない。
テレビドラマを思い出してもらうと分かりやすいが、「水戸黄門」あれば海外では理解されない。なぜなら、あのドラマは「黄門さまは偉い人。知ってるよね?」という視点で作られている。それを知らないで見ると、クライマックスで印籠を見せ、皆がひれ伏すシーンの意味が分からない。同じように織田信長、知っているよね?という暗黙の了解で、作られる時代劇が多い。坂本龍馬知っているよね? その辺を描かずに物語を進める。
「日本人同士だから分かるよね?」という発想なのだ。日本史を知らない外国人が見ると????となる。テレビドラマだけでなく、日本では映画もそんな発想で作られることが多い。その点、アメリカ映画は国内に多様な人種、宗教、国籍の人たちを抱えているので、誰でも分かるように物語を作る。だから、世界中の人たちも見れる。
日本の黒澤明監督。彼の映画も実は、どの国の人が見ても分かるように作れている。「日本人なら分かるよね?」という発想で時代劇も作っていない。だから、アメリカでも理解され、高く評価される。が、これは映画だけの話ではなく、日本人はどうしても、日本の習慣やルールに縛られることが多く、「言わなくても分かるよね?」というところがある。全てを論理的に、相手が分かりやすく説明するというのが苦手な国民だと思える。だから、外交が下手なのだが、映画も同じ。
アメリカで評価されている監督は皆、それを理解。ちゃんと外国人にも分かる形で映画を作っている。伊丹十三監督も、周防正行監督もそうだ。留学中に学んだ大切なこと。だから、僕がシナリオを書くときは、必ず外国の人が見ても分かる形で物語を作る。「日本人なら分かるよね〜」という発想では絶対に駄目。以前よくプロデュサーが「そんなこと、いちいち描かなくても、みんな知ってるよ〜カットカット!」なんて言っていたが、その発想が海外に発信できなくなる最大の理由だ。
今回の「向日葵の丘」も、これまでの3作と同じように、アメリカ人が見ても、ヨーロッパの人が見ても、アジアの人が見ても感動できるように作ってある。とはいえ、やはり、実際に上映されるまでは心配。英語字幕の確認作業をしながら、来るべき海外上映のときのことを想像している。

2014年09月29日 Posted by クロエ at 11:33 │Comments(0) │思い出物語
「向日葵の丘ー1983年・夏」監督日記 英語訳の確認は続く!

午前中から続けている英訳確認作業。夜になっても続いている。単に単語や表現をチェックするだけでなく、疑問に思ったところは英語が得意な友人に問い合わせて意見を訊く。
が、人はいろんなことをいうので、最後に結論を出すのは自分自身。一つの意見が多いからと、それを採用したりはしない。アートは多数決ではない。むしろ、個性的で多くの人が支持しないものの方が結果として、より多くの人に採用されたりする。英語でも、日本語でも、言葉の表現でも同じだ。
その台詞のニアンスを伝えるには、どういう翻訳、どういう言葉を選ぶべきか?あれこれ考える。昔の映画のタイトルを調べたりもするので、時間がかかる。

2014年09月29日 Posted by クロエ at 11:31 │Comments(0) │ポストプロダクション
「向日葵の丘ー1983年・夏」監督日記 英語訳もなかなか大変な話。

日曜だというのに、朝から英語字幕原稿の確認。英訳してもらったものを、送ってもらいチェックしている。台詞を英語にするときは、単に直訳するのではなく、アメリカ人が分かるように言葉を置き換えたりする。
僕がロサンゼルスに留学していた頃。日本映画が公開されると映画館に行き、日本語の台詞で英語の字幕スーパーで映画を見た。日本語の台詞がどんなふうに英訳されているのか?も興味のひとつだった。
難しいのは固有名詞。坂本龍馬とか、織田信長というと日本人なら誰でも知っているけど、アメリカ人は誰も知らない。そんなときは別の名前を使ったりする。「逆噴射家族」という映画では犬の名前が「二宮金次郎」だった。が、それではアメリカン人は判らない。といって「ジョン」とか「ジョージ」にすると意味が伝わらない。で、「リンカーン」という名前になっていた。苦労して偉くなった人の名前というのを大切にしたからだ。
また、「サムライ」や「ヤクザ」はそのままで通じる。わざわざ「ジャパニーズ・ウォリア」とか「マフィア」と置き代えなくてもOKだ。それから劇中で映画のタイトルが出てくるときは要注意。そのまま直訳してもアメリカ人はどの映画か?判らない。
「タイタニック」とか「インデペンデンスディ」なら、そのままでいいが、「ダーティハリー4」は「Sudden inpact」。「ランボー」は「First blood」だ。また、「ドラゴンへの道」は2つ英語タイトルがあり、「The way to the doragon」と「Return of the Drogon」がある。
ややこしいのは「ランボー2」は「Rambo 」「ランボー3」は「Rambo3」ただ、英語ができるだけでなく、その辺を知らないと英訳はできない。今回、お願いした方はその辺も熟知してくれているので、ありがたい。
時間ができたら早く読みたい小説もあるのだけど、なかなか作業が終わらない。このあとも、ポストプロダクション作業が山積み。とりあえず、がんばる!

2014年09月28日 Posted by クロエ at 16:09 │Comments(0) │ポストプロダクション
「向日葵の丘」ー監督日記 モノローグ録り

先日はスタジオを借りてモノローグ録音。
MAスタジオに入ると、いよいよ完成が近い!という気持ちになる。
でも、本日1日では終わらないので、別日にも作業する。
スタジオ入り前に、元気が出るように昼飯はこれ

差し入れに以下を頂いた。


2014年09月28日 Posted by クロエ at 16:07 │Comments(0) │ポストプロダクション
「向日葵の丘」仕事ばかりしていると感性のアンテナが錆び付き、時代に取り残される?

「青い青い空」(2010)を完成させるには4年かかった。というのも、題材である書道を学び、製作費を集め、ロケ地である浜松を勉強していたら、歳月が経ってしまったのだ。スタッフが集まり、撮影準備を始めるまでは全て1人でやっていたので、休養も、趣味も、バケーションも、余暇もなく、ひたすら映画製作を進めていた。
そんなことをしていると、世の中の動きが分からなくなる。今、何が流行っているのか? 世間はどうなっているのか? 景気はどうなのか? 誰が人気あり、どんな歌がヒットしているのか? 一見、どーでもいいようなことだが、そんなことから人は時代を感じるのだ。特に映画を作るような仕事をしている者は、その辺に敏感でなければならない。映画は時代の反映。時代を感じていないと、観客の共感を得られる作品は作れない。
だが、忙しいだけでなく、歳を取ると、時代を感じる力も衰えてくる。感性のアンテナが錆びてくる。特に男性は要注意だ。時代に取り残され、古びた情報を得意げに話し、時代遅れの価値観を振り回して、若い人に嫌われる(所帯持ちなら妻にも阻害される)。そんな大人たちを嫌というほど、見て来た。が、そのとき自分自身がそうなってしまう危機感を持った。「青い青い空」を完成。劇場公開をしたあと、過労で倒れ、半年間も寝たきりになった。医者からは「過労死」するので休め!と何度も言われたのを無視して、仕事を続けたからだ。
その上、映画監督というのはそれに見合う報酬がもらえるどころか、残るのは借金の山。という悲しい仕事。さらには、時代が分からなくなる。で、寝たきり時期にリハビリ。手軽に時代を感じられるのはテレビ番組。「下らない番組を見ても時代なんて分からないよ?」と言われそうだが、下らない番組が作られるということから、その背景を探れば、時代が見えてくる。
驚いたのは、少し前までパネラーだったお笑い芸人たちが、司会をしていることだ。「ボキャブラ天国」に出ていた海砂利水魚がバラエティ番組の司会? 名前もクリームシチューになっている? 最初は良く似た別のコンビ?と思った。そのくらいに世間から取り残されている自分に気づく。他にも見たことない若手芸人がたくさん出ていて、つまり、世代代わりが行われていたのだ。パネラーだった若手芸人がベテランとなり司会者に、そしてさらなる若手が出て来てパネラーになる。
昔は、「今、どんな歌が流行っているのかな?」と思えば、「ザ・ベストテン」を見ればよかった。が、今、歌番組はごく僅か。皆、どこで歌を知るんだろう?と思えるほど。CMを見ても、知らない若手俳優。ん〜、リハビリは時間かかるぞーと思いつつ。スタートした。とにかく、起きて外に行く体力がないので、最初はテレビを見るのさえ、辛かったが、回復して来てから、十数年振りに本を読み、たまっていたDVDを見る。
いつか読もうと買っておいた村上春樹の「ノルウエーの森」(1988年発売)を2011年になってやっと読んだ。同じ著者の小説を続けて読み、録画してDVDに焼いていたのに見ていない衛星放送の映画を見た。そんなことをしていて、テレビではしっかりと報じられない原発事故に興味を持ち、仕事とは関係なしに勉強を始めた。
「映画化にする!」なんて思いはなく、ずっと寝たきりでテレビを見ていたにも関わらず、14万人もの人が福島から避難していることさえ知らなかった(当時、ほとんど報道されていなかった!)ことにショックを受けたのがきっかけ。それが、やがて「朝日のあたる家」に繋がる。
その「朝日」をスタートさせたのが2012年。そこからは取材、そして製作費集め、シナリオ執筆、ロケ地での活動と、またまた、テレビを見る暇もないほどに忙しくなり。そのまま撮影。編集。完成。公開。宣伝。と休む暇なし。
その間に「向日葵」がスタート。「朝日」の舞台挨拶ツアーの合間にロケハン。年が明けてからシナリオ書き、そして撮影、編集で、もう現在に続く。「青」のリハビリ期以来、3年近く、また、時代から遠ざかっていた。
こうして、錆びたアンテナはさらに錆びて、感性が古くなり、若い頃に軽蔑したおじさんたちのようになって行くのだ。危ない危ない! ようやく編集が終わり、まだまだ、多忙ではあるが、まずはテレビ番組を見ることからリハビリを始めたい。まだ、じっくりテレビを見る余裕はないが、飯を食うとき、朝起きたとき、寝る前には、録画した番組を出来る限り見ている。ようやくリハビリ開始だ。

2014年09月28日 Posted by クロエ at 16:04 │Comments(0) │思い出物語
「向日葵の丘」懐かしいものを発見。ペンギンの***?

懐かしいもの発見! 若い人にはこれが何だか分からないかも? 現在、仕上げ中の映画「向日葵の丘」の舞台となる1983年に人気だったグッズ。

1983年に人気だったペンギンキャラ。そのカセットテープのキャリングケース。聖子ちゃんの歌♫「Don`t kiss me baby~」が聴こえてきそう?
こんなふうに持ち運びできます!

2014年09月26日 Posted by クロエ at 16:59 │Comments(0) │1983年の話
「向日葵の丘」監督日記 世界公開を目指して字幕スーパー制作!

僕の映画。どれも何十億円という超大作ではなく、低予算のものばかりだが、「ストロベリーフィールズ」から、前作の「朝日のあたる家」まで、全て海外で上映。そして各地の映画祭で好評を得ている。
新作「向日葵の丘」も同様に、海外での上映は射程距離! 今から英語の字幕スーパーを制作している。さすがに自分で英訳のは大変、特別のスキルが必要なので、出来る!方にお願い、上がったものを確認させてもらう。
果たして、「向日葵の丘」は海外の人たちにどのように映るのか?
え? 「サムライが出て来ないとウケない」って? そんなことはない。
「青い青い空」も「朝日のあたる家」もアメリカでは拍手喝采!絶賛だった。今回も楽しみだ!
向日葵の丘」も目指せ!ハリウッド。
前作「青い青い空」LA上映のときの日記を紹介
=>http://takafumiota08.blog.so-net.ne.jp/2011-05-01

2014年09月26日 Posted by クロエ at 16:56 │Comments(0) │海外公開
「向日葵の丘」自分の知らないことを、自分の立場を考えずに、あれこれ言う人たち

「監督の****という発言はいけないと思います。品位が下がりますよ」とか「あまり細かいことを気にしない方がいいよ」とか「あなたの考え方は違いますよ。もう少し謙虚になった方が」とか、(一時期は「野菜を食べましょう!」「野菜が不足していますよ〜」というのも多かった)これらは基本、好意で書かれたと解釈する。だが、言い換えれば「大きなお世話」だ。
なぜ、そんな説教じみたことを言って来れるのか? どういう立場で言っているのだろう? 説教、アドバイス、助言、注意。いずれにしても、相手をよく知っていてこそ言えるし、相手にも伝わる。親、先生、先輩から言われるのなら分かる。が、FB上でしか知らない相手に対して、1、2度会っただけの人が、あれこれ「考え方」や「プライベート」を指示するのはどうだろうか?
相手はあなたの部下でも、後輩でも、子分でもない。親しい友人ですらないのだ。ネットを通して交流するFB「友達」にしか過ぎない。相手のことをあなたはどれだけ知っているのか? プライベートや考え方を理解しているのか? そんな人は、あれこれ指摘、助言する立場にはないと考える。
さらに、一般の方が書き込むコメント。映画界の常識やルールを知らないから的確な意見でないことが多い。或いは、記事をしっかり読まずに誤解した発言がやたらある。指摘が完全な間違いであること。勘違いであることを説明するには長い返事を書かねばならない。
なぜ、間違ったコメントに対して、時間と労力を使い返事せねばならないか? それでなくても映画製作は時間との戦い。そんなコメントは時間を奪い、苛立たせるだけの存在。そこで、一歩進んで、今後、その種のコメントは説明も警告もなしに削除することにした。
コメントをくれる人は好意であり「監督のために」と思って書き込んでくれるのだろうが、それらは僕のためにならず、ただ時間を奪い。さらに勘違いした人を引き込んでしまう悪循環。神経をすり減らす編集時に読むとイラ立つだけだ。
だから、「提案」とか「アドバイス」はもう書き込まないでほしい。もし、僕の記事を読み。「この人、間違っている!」と思っても、何も言ってくれなくていい。「私が言ってあげなきゃ」とか正義を感じないでほしい。それは応援にはならず、こちらを困惑させるだけだ。
だが、別の視点で見ると、それだけ多くの人が応援してくれるようになったということ。その意味でおせっかいな人が増え、自分の立場を考えない人も出て来たたということだ。同時にうるさく言わないが、応援してくれる人も増えたということ。実はそんな方々が一番多い。うるさく言うのは目立つが少数派である。「朝日」以前では考えられない反応。いずれにしても、多くの人が応援してくれるのは嬉しいこと。
FBだけではない。多くの人は自分の立場や相手との関係性を考えず。好意と思い、アドバイスと考えて、あれこれ言う。が、当人は迷惑であることが多い。なのに「俺が言わねば!」と正義を感じて進言。それに気づかない。悲しい話だ。「私はそんなことしてないかな?」「もしかしたら...」そんなことを実感するのもFBを続けるメリットかもしれない...。