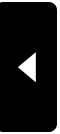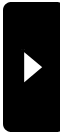「向日葵の丘」なぜ、人は他人の痛みが分からないのか? 他人事で済んでしまうのか?

なぜ、人は他人の痛みが分からないのか? 他人事で済んでしまうのか?
学生時代にT君という友達がいた。彼は非常に陽気で面白い奴だが、少々問題があった。僕が友人に貸した金がなかなか返って来ず、イライラしていると「せこーい!1万2万の金いいじゃねーかー」と笑う。が、当時、僕は月10万円で生活していた。貯金はない。貸した2万円が返って来ないと、その月の生活がヤバくなる。
ある日、T君自身が貸した5千円が返って来なくて、彼がイライラしていると逆に「せこーい。5千円くらいいじゃねーかー」というと、感情的になり「何言ってんだ。5千円は大金だぞ! バカなこというんじゃない!」と激怒した。
彼はそんな性格で他人の痛みは笑って過ごすが、自分のことはすぐ感情的になり怒り出す。日頃は陽気で面白い存在だが、それが仇となり、多くの友達はやがて去って行った。彼は極端だが、多くの人は彼と近い部分があるのではないか? 人の不幸を聞いても「ふーん。大変だね」で終わり。でも、自分が被害に遭うと慌てふためく。
僕は原発事故後の福島に行き、被災者の方に話を聞き、それを痛感した。事前に勉強はしていたが、彼らの苦しみを理解できていなかった。理屈では分かっていたが、放射線で立ち入り禁止となった仕事場、畑、家を見て、彼らの話を聞いて何もいえなくなった。僕もT君と同じなのだ。他人の痛みを想像し、自分のことのように感じることが出きていなかったのだ。

でも、新聞やテレビのニュースを見ても地元の人たちの苦しみは伝わりにくい。その痛みをどうすれば伝えられるか?を実践したのが「朝日のあたる家」だ。が、現実の中では、言葉や活字だけで人の悲しみを知るのは本当にむずかしい。この間まで「福島、大変!応援しなきゃ〜」と言っていた人が「次の選挙は景気回復が党を選ばないと」と言う。
ある製作会社に監督料の支払いを拒否されたことがある。何ヶ月も働いて、ノーギャラ。抗議しても「金はない」という。そこでスポンサーに直談判した。その人は業界の人ではないが映画作りに投資している。こう言われた。「監督は映画愛のある人だと思っていたのに、結構、金に細かいんだね? あなた、金のために映画をやってるの? 失望したよ」
驚いた。そんなことを言われるとは思わなかった。が、彼は僕の働きを見ていて「よくがんばるなあ。映画愛のある人なんだ。お金のためにやってる訳じゃないんだ」と評価していたようだ。でも、その僕がギャラの支払いを要求したので「失望した」と言うのだ。ただ、その前に、何ヶ月も働いて監督料がもらえないと生活ができない。家賃も払えないということは想像しない。
監督料といってもサラリーマンの月給と大差ない額。いや、それより少ないだろう。それ以外の収入がないことも分かっているはず。生活が破綻する。でも、考えない。学生時代のT君。決して特別ではなかったのかも?と思えた。
しかし、僕も勉強してはいたが、福島の人たちの苦しみを想像仕切れなかった。その意味では同じかもしれない。人はなぜ、他人の痛みを想像できないのか? 他人ごとで済ませることができるのか? そのくせ、自分が被害に遭うと、怒りを爆発。「何で、この苦しみを皆、理解しない!」と思ってしまう。
「朝日のあたる家」神戸で上映してほしいという熱いリクエストがあった。聞くとこう言われた。「我々も震災でもの凄く大変だった。だから、福島の人たちの気持ちがもの凄く分かる。だから、映画を見て、自分たちができることを考えたいです」
胸が熱くなった。が、神戸の映画館は全て上映拒否だった。自主上映が解禁になったとき、一番に依頼が来たのは神戸だった。有志の方々が自主上映会を開いてくれた。劇場は超満員。皆、涙、涙で映画を見てくれた。そのことを思い出す。

2015年05月20日 Posted by クロエ at 00:21 │Comments(0) │MyOption
「向日葵の丘」町おこしのための地域映画が成功しない理由?③ 自分で首を絞める宣伝

映画を使って町おこし。日本各地でそんなチャレンジが続いている。地元で映画撮影がされれば、大きな宣伝になる。テレビ、新聞等の広告を出すより遥かに経済的で、それも長期間に渡って宣伝することができる。しかし、その多くのチャレンジが失敗している。特に問題が大きいのが宣伝である。
地元で映画に関わった方々の多くは素人であり、映画製作の知識は少ない。が、それはスタッフと力を合わせてがんばればなんとかなる。しかし、宣伝というのはいろいろと勘違いしやすく、地元の方が間違った方向にがんばってしまうことが多い。結果、素敵な映画が出来ても、作品に興味を持ってもらえず、ヒットしない。つまり、町の宣伝にならないことが多い。説明しよう。
完成した映画はまず、東京で公開されることが多い。ヒットすれば全国の映画館で上映される。地元は製作会社、或は宣伝会社に対して、いろいろ要望を伝える。会社側も多大な協力してもらっているので、なるべく要望を受け入れるようにする。そんなときよく出されるのが「***市オールロケ作品」というキャッチコピーを使ってほしいということ。だが、これは命取りになることを多くの人は分かっていない。
地元としては「わが町で撮られた映画であること。必ず伝えてほしい」という思いがある。「映画を観て、きれいな町だなあ〜と思っても、そこがワシらの町であることが分からなければ宣伝にならない。あれだけがんばって支援したのだから、それは伝えてもらわないと!」そう考える。一見、なるほど、そうだと思う人も多いだろう。が、これが、そもそもの大間違い。
そのキャッチコピーを一般の人。その町とは無関係の人が観たらどう思うだろう?「***市? どこにあんの? 何県? 聞いたことないなあ。そんな町で撮った映画にゃ興味ないよ」となる。考えてほしい。京都、奈良、横浜、或は北海道のような有名な観光地でロケしたのであれば、多くの人が興味を持つが、名もなき、小さな町でロケしたことは、一般の人の興味は惹かない。

なぜ、映画は有名な観光地で撮影するか?といえば、多くの人が興味ある町だから、関心を持ち、映画を観に来てくれるから、観光地でロケするのだ。つまり、「***市オールロケ作品」というキャッチは宣伝にはならない。人々の気持ちを掴まないのである。にも、関わらず、地元は「ワシらの町で撮影した映画だ。何て誇らしい。それを全国に伝えよう!」思ってしまうのだ。
ここには大きな勘違いがある。地元からすれば「わが町でロケしたこと」を誇りたいが、外部の人からすれば「あーそう?良かったね」で終わりなのだ。「だから観たい!」にはならない。つまり「***市オールロケ」というコピーは宣伝ではなく「自慢」でしかない。それではアピールしない。
これが「京都、オールロケ」とか「函館市、オールロケ」と有名観光地であるなら、「へーーそれなら観たい」となるのだが、無名の町でいくらロケされても、人々の関心は惹かない。それどころか映画ファンが聞けば、こう思うだろう。「ああ、今、流行りのリージョナルムービーかあ。映画で町おこしって奴だな。どーせ、地元の名所案内をして、ストーリーそっちのけで町をアピールする詰まらない映画だ」と思われてしまうだろう。
そう、実はその手の映画が多い。地元が製作費を出したことで、シナリオやロケ場所にあれこれ口を出し、映画ではなく、地元のPR映画になってしまうことがよくある。そのために映画はヒットせず、評価もされない。映画ファンはそれを知っているので、無名の町でロケされた映画で、地元を強くアピールする作品は敬遠することが多い。
そんな現状を知らず。わが町で撮られたことを伝えることに地元は力を入れて、自身で首を閉めてしまう。「宣伝」というものの意味を勘違いしているのだ。もし、映画ではなく、テレビCMなら「美しい***市」をアピールする必要がある。そのためのCMだ。が、映画の宣伝は「町の宣伝」ではなく、「映画」の宣伝なのだ。その映画の宣伝で「町」の宣伝をして何になるか?ということ。

分かりやすく言えば、その町で取れた野菜で作ったスナック菓子を売り出すとき。北海道産のジャガイモを使ったなら「北海道のスナック」といってもアピールする。北海道は人気ある町。イメージもいい。だが、「***市の野菜を使ったスナック」といっても、ほとんどが興味を持たない。**市を知らないからだ。そうではなく、そのスナック自体のおいしさをアピールすることが大事。「ん? これ美味しい! どこの野菜を使ってんだろう?」と思って始めて、それがどこの町かに関心を持つのだ。
映画も同じ。「****市オールロケ!」と告知するのではなく、映画の面白さをまずアピールすることが大事。感動できるのか? 笑えるのか? 泣けるのか? そんな映画の魅力を発信。まず、映画を観てもらった上で、「あーー感動した。いい映画だった。風景もきれいだったし、どこの町なんだろう?」と思って、始めて町に興味を持つのだ。
それを最初から、それも宣伝で「地元」をアピールしては、その段階で人々は関心をなくすのである。それが地元の人には本当に分かり辛いようで、何処の町でもすぐに「***市オールロケ」と宣伝で言ってほしいと言いがち。だが、それは大きなマイナス。
僕も地方を舞台にした映画ばかり撮っているが、宣伝でその手の表現は絶対に使わない。町の人から「ぜひ」と頼まれることもあるが、受け入れない。それは支援してもらった町のためにならないからだ。その辺を説明し、町の名前は宣伝では使わない。それより、映画がいかに感動的なもので、涙があふれる素敵な物語であることを伝える。その映画を観てくれれば観客は必ず、こう思う。
「映画もよかったけど、ロケ地もよかった。美しい風景。ぜひ、訪れたい」
そう思ってもらうために、僕は町の歴史を学び、町を勉強し、町を好きになってから撮影する。町の四季を1年がかりで撮る。でも、宣伝で町の名前は出さない。それは結果、映画への関心をなくせることだからだ。宣伝というのは「映画」を宣伝するものであり、「町」を宣伝するものではない。町を宣伝するのは「映画」なのだ。その映画の宣伝で「町」を宣伝したらアウトなのだ。
その辺が分からず「ワシらの町でロケした映画じゃ!」と宣伝し、そっぽ向かれる映画が結構ある。東京公開で映画館に来るのは、町の出身者ばかり。一般の人たちの興味を惹くことはない。お金をかけ、汗を流し、みんなでがんばって、自分で自分の首を絞めること。残念ながら地方ではよく行われている。

2015年05月13日 Posted by クロエ at 14:14 │Comments(0) │MyOption
町おこしのための地域映画が成功しない理由?② 他力本願が町を滅ぼす?

地方活性化のために、地元を舞台にした映画を作るという活動。各地で行われているが、多くの街は映画を作るところまで行かない。話合をしただけで結局、頓挫ということが多い。僕は毎回、地方を舞台に映画を作るので、その辺の相談をときどき受ける。町の人に会い、話を聞くとと問題点が見えてくる。あるとき、ある町で町おこし活動をする年配の男性と話した。
「この町は観光地でもなく、有名な史跡や寺もないんです。でも、映画撮影がされれば町をアピールすることができる。観光客が来てくれる。『寅さん』や『釣りバカ日誌』のような映画が来てほしいんですよねー」
確かに全国公開される映画の舞台となれば、大きな宣伝になる。対費用効果も何億円にもなる。そんな映画撮影を誘致したいというのは分かる。が、先に上げたようなメジャー映画はそれなりに有名な町でしか撮影しない。本当に何もない田舎町で撮影して「次回作の舞台は***市」と宣伝しても、観客にアピールしないからだ。

北海道とか、温泉地とか、古都とか、それなりに絵になり、由緒ある町で撮影してこそ、観客はその映画を見たい!と思うのだ。そう考えれば、そんな大作映画のロケがその町に来ない。が、その人は「そんな映画が来てほしいんですよねー」と訴える。
そこで映画界の事情を説明した。映画会社はそれなりの町で撮影したがる。名もなき町で撮影しても客の関心を惹けないから。だから、有名な映画を誘致するのはむずかしい。でも、低予算の映画であれば、製作費の一部を負担するとか、安く泊まれる宿を提供するとか。いろんなメリットを提案すれば、興味を持つはずだと。だが、その人はこういう。
「低予算の、誰も知らない映画が来てくれても、あまり宣伝にはならないですよね? やはり全国公開される。有名俳優が出た映画の撮影でないと意味がないんですよ」
呆れた。自分の町には何もないことを知りながら、大手映画が来てくれることを願う。低予算でもそれなりの宣伝に繋がるのに、一発で大きな成果が上がる大手でないと嫌だという。彼は続ける。

「それとも国が補助金や支援金を出してくれて、それで映画を作ればいいんですけど、なかなか、そんな制度もないんですよ」
???? その人の話を聞いていると、自分たちは何もせず、国や映画会社に何かしてくれ!といっているように聞こえる。自分たちで努力すること。何かないのかと訊くと、
「いやーワシらもがんばってますよ。地元出身の議員先生に、映画製作の補助金はないか? 何かそれなりのものを持ってきてくれないか? 何度も陳情に行きました。映画会社に資料を送って、ロケをお願いしたこともあります」
んーーーだんだん、イライラしてきた。で、こう訊いた。自分たちで製作費を集めて、映画を作ろうとか、一部製作費を投資するから、ロケに来てほしいという交渉はしないんですか?
「だって、この町は金ないから、誰もそんな余裕はないよ。地元産業はダメだし、工場誘致も失敗。農業もダメだし、あとは観光で稼ぐしかない。そもそも、金があったら、映画なんか誘致しないよー」

ダメだ!!! その人の考えを一言でいうと「他力本願」自分たちの町は経済的に大変だから、国や映画会社が地元で映画を作り、町の宣伝をしてほしいと言っているのだ。そして、自分たちは金がないので何もできない。哀れな存在だと主張する。何の努力もしていない。
その町で他の人たちとも話をしたが、ほとんどが同じ考え。次第に分かって来た。その町は経済的に大変といいながら、田んぼの中に豪華なコンサートホールがあったりする。他にも美術館があるが、客はほとんどいない。でも、維持費が大変で、それも町の財政を苦しめているという。これで分かった。
つまり、この町は10年ほど前に、代議士さんたちに頼み地元活性化のために、コンサートホールや美術館を建てたいと陳情した。それが実現、80%近くが国の補助金で立派な建物ができた。が、客は来ない。維持費が大変。どーしよう。映画で町おこしが流行しているらしい。大手の映画が来てくれれば宣伝になる。うちの町の来てくれないかな? よし、議員先生に頼もう。....という流れなのだ。
その町に限ったことではない。多くの地方は自身で努力せず、地元の議員に陳情し、国の補助金や支援金をもらおうとする。が、美術館を建てても、建設時にゼネコンが儲かり、多少は町も景気がよくなるが、完成すれば維持費で苦しむ。そこまで考えずに流行りに乗ってしまう。国や議員に頼るばかりで、自分たちで何かをしようという気がない。
「いやーそんなことないですよ。議員先生にお願いに東京まで何度も行きましたよ。仕事休んで皆で。大変でしたよ〜」
もー嫌だ。考えれば自分たちで映画を作ることだってできるのに「補助金だ」「大手の映画だ」なんていっているからダメなんだ。が、その人がそんな考え方をするようになったのも分からないではない。
日本の行政は、中央で決め、それを地方に押し付ける。地方は考えなくてもいい。政府が決めたことを守っていればいいというシステム。黙っていても中央から補助金や支援金がもらえるが、決められた使い方しかできない。つまり、何十年も間。言われたことしかしていない。だから、何かあれば、陳情して、金を出してもらう。国や映画会社に何とかしてほしい。と頼むことしか思いつかないのだ。

もちろん、自発的にいろんなことを考えて実践している町もある。が、他力本願で自分たちは何もしないで、「困ったなー」と言っている町も結構多い。町おこしの問題だけではない。就職を控えた若い人たちも同じ発想をしている。自分は努力せず。何ら特別な技術や能力がある訳でもないのに「就職は有名企業がいいなー。誰も知らない会社に入るのは恥ずかしい」「どこか、オレを入れてくれる大手企業はないかな」なんていっている。
同じパターン。子供の頃から与えられたことをするだけの教育を受けて来たからだ。教育では言われないことをすると注意されることも多い。だから、与えられたことだけをする。何度も書くが「考える力」を育てない日本の教育。そんな子が大きくなると、先の年配男性と同じ発想になるのだろう。その人。最後にこういった。
「監督さん。どこか大手の映画会社をまわって、この町で映画撮影してくれるところ探して来てくれませんか? ワシらがいうより、効果あると思うんですよ」
どこまで行っても「他力本願」とても映画作りまで行かない....。町おこしもむずかしい。でも、これが多くの地方での現実なのである

2015年05月12日 Posted by クロエ at 15:56 │Comments(0) │MyOption
「向日葵の丘」町おこしのための地域映画が成功しない理由?①キャスティング

地方自治体や町のグループが中心となり、映画ロケを誘致して町のアピールをしよう!という取り組みが各地で続いている。僕も地方を舞台に映画を撮り続けているので、ときどき相談されるが「それではダメ。必ず失敗する」ということが多い。彼らは映画で町をアピール、観光客を呼んだり、町の魅力を全国に伝えたいというのに、それには繋がらない努力ばかりしているからだ。
要因はいくつもあるが、そんな中から今回はキャスティングについて説明する。ある町で映画を作りたいという相談を受けた。マイナーな田舎の市なので、大手映画会社は見向きもしてくれない。だったら、自分たちで映画を作ろう!と考えた。そこの関係者と縁があったので、相談にのった。
市役所の大会議室に、町の顔役、実力者、観光課の職員、商工会議所の代表、町では最大手の工場の社長、婦人会の幹部等、30人近くが集まった。彼らの希望は先に上げたように、映画による町おこし、全国へのアピールだ。そこで具体的な希望を聞いた。ある年配男性が答える。
「やっぱり映画なんだから、スターを呼びたい。高倉健がいいなあ」
「だったら、女優は吉永小百合だ」
「そーだなー、きれいどころをズラッと並べた映画にしようぜ」

この段階で不安になった。で、質問した。今回の製作費をどのくらいに考えているのか? だが、誰も答えない。もちろん、彼らはプロではない。予算と言われても困るだろう。そこで説明した。
例えば、健さんが出てくれるような映画を作るのなら、3億円以上の予算が必要。きれいどころがズラーなら5億円以上を考えてほしい。と、すると、先の年配男性が、
「そんな金どこにあるんだよ! バカなこと言ってんじゃないよ」
その言葉を聞き、映画をどう作るか?ではなく、映画作りの基本から説明していかねばならないことを感じた。「映画を作りたい」といい、相談に乗ってほしいといわれ、僕は自腹で東京から電車で1日近くもかかる田舎町まで来ているのに、彼らは映画作りにのことをほとんど勉強していないことが分かった。
そこでまず、高倉健さんのギャラだけでも膨大な額。それで別の映画が1本作れる額であること。もし、本当に健さんに出てほしいのなら、それだけの予算をどう捻出するか?を考えるのがスタート。でも、3億円以上の製作費を用意できないのであれば、町で捻出できる額で映画を製作。その範囲で呼べる俳優を選ぶべきということ。

そう説明すると、場内はざわついた。「映画ってそんな金がかかるの?」「健さん呼べないんなら意味ないな」「吉永小百合のギャラも高いのかしら」そんな声が聞こえた。もう、先の言葉「そんな金どこにある」で分かったが、彼らには映画作りということに全くリアリティがないのだ。もちろん、カタギの方なので当然なのだが、この場は真面目に「町おこしのために映画を作る」ことが議題。
にも関わらず、そんな言葉が出るということは、「健さん。うちらの町の映画に出てくれたらうれしいなー」という夢を語っただけということなのだ。それが小学生の発言なら分かるが、町の実力者の1人で、町のアピールのための大事な会議で、夢を語り。「そんな金どこにある」なんて答えをするというのは、どういうことか?
その方は決して不真面目ではなく、真剣に映画による町おこしを考えて参加しているのだと思うが、そんな答えをするのは、映画製作にあまりにもリアリティがなく。現実問題として考えることができないということなのだ。そして、映画雑誌をいくつか読めば、分かる映画界の情報を仕入れることもなく、この会に参加したのだ。
まず、そこに大きな問題を感じる。もし、これが映画ではなく、化学工場誘致であれば、その工場は何を作り、どんな排出物を出し、公害はどうか? そして、どのくらいの収益を町に落とすか? 等。工場と製品について勉強するはずだ。ではないと、あとあと大変なことになる。

にも関わらず、その人は映画についてまるで勉強もせず。自分の夢を語り。「そんな金どこにある?」と言い出す。他の人たちの発言を聞いても近いものが多い。つまり、この町の人たちは「映画ロケは町おこしになる」と聞いて「そりゃいいやー」と盛り上がり。ほとんど勉強もせずに、顔役が集まり、実業家たちがそこで単なる希望を語ったということなのだ。
しかし、そのあとに出た発言も驚くべきもの。僕の映画ではロケ地出身の俳優さんに出演してもらう。そのことで地元も盛り上がり、その俳優さんも張り切ってくれるからだ。その話をすると、別の男性がこう言う。
「いいねー。だったら、出演者は全員、この町出身の俳優にしよう!」
「そりゃ、いいわー。そうしよう!」
場内は盛り上がった。が、僕は頭を抱えた。事前にその町出身の俳優を調べていたが、名の通った人は2人だけ。無名の俳優を調べても、その町出身の俳優は何人いるのか? 質問した。
「そんなことは知らねーよー。でも、この町で撮るならこの町出身の俳優にしなきゃー」
頭が痛くなった。だったら、地元の劇団か何かを使って映画を撮った方がいいかも? 何より、キャスティングというのは、その役に合った俳優を選ぶことが大事。その前に「この町出身」という規定を作ってどーする? 例え、出身俳優を何十人も集めても、役に合っていない俳優をキャスティグすることになる。それはもうクオリティの高い映画はできないということ。

何より、俳優が全員、その町出身ということは、映画のプラスにはならない。「へーーそれは凄い」と思う映画ファンはいないだろう。喜ぶのは地元の人だけ。しかし、どこの町で相談を受けても同じ発想の人は結構多いのだ。つまり、映画を使って町をアピールするというテーマから外れ、自分たちが楽しい、盛り上がれることをしたい。
健さんを出演させたい。きれいどころをズラー。地元出身俳優ばかりで。これらは皆、地元の人がそれだと面白いなー。撮影も楽しみだ。という思いから出た発言だ。町をアピールすることは置き去り。「この町に健さん来ればいいな」「地元出身者ばかりだと、皆、知った顔がいて盛り上がる」そういう発想。
3時間を超えて、映画作りとは何か? 地元をアピールするとはどういうことか? 映画はなぜ金がかかるか? どう回収するか? 等を説明したが、集まった方々は「よく分からんなあ〜」という顔。町の財政が切迫し、何かしなければという危機感はお持ちであり、だから、映画で町おこしを考えているはずなのに、そこはやはりリアリティがないようだ。

結局、その町で映画製作は行われなかった。そして、この記事を読んだ多くの人は「その連中がバカなんだよ」と思うかもしれない。或は「そんな奴、田舎でもいないだろう?」というかもしれない。が、これが地方の現実。その町の実業界では実力者でも、映画に関してはリアリティが持てず。夢を語ることしかできない。こんな方々と僕は数多く、出会った。
けど、これは彼らだけの問題ではない。俳優志望、映画監督志望、或は作家希望の若者も同じ。華やかな芸能界を夢見ているだけで、実際に俳優や監督がどんな仕事をしているのか? その厳しい現実を知る人は少ない。それを勉強して、知ろうとする若者も少ない。憧れだけを抱き、専門学校や演劇学校に通う。が、卒業しても仕事はない。具体的な方法論を持たず、憧れているだけでは目的は達成できない。そんな若者たちと、その町の顔役たちは同じなのだ。
もし、真剣に映画を作り、町おこしをし、全国にアピールするなら、他の事業と同じように、その分野を勉強し、理解し、夢を語るのではなく、現実の中で何ができるか?をまず把握することだ。その町の存亡のための戦い。その手段が「映画作り」というだけのこと。その映画を「夢」で語ってはいけない。

2015年05月11日 Posted by クロエ at 13:55 │Comments(0) │MyOption
「向日葵の丘」友達を探しFacebookで「友達」を求める寂しい若者たち? そして悲しい結末

Facebookを始めた頃は「友達」は実際の友達だったり、顔見知りだった。が、月日が経つにつれて、1度しか会ったことのない人。会ったことのない人も増えて来た。それでも名前やアバターは記憶していたが、あと4人で「友達」が2000人になろうとしている今では、誰なのか?分からない「友達」もかなりいる。
もちろん、その中には「友達」というより、「監督を応援してます」という「応援団」的な方、「監督の書く記事を読みたいんです」という「読者」タイプの方、映画作り、舞台裏に関心がある人等、いろんなタイプに分かれている。が、中にはFacebook「友達」を現実の友達と同じ存在だと思っている人もいて、ときどき困惑する。
現実の友達でも、最初は距離を置き、プライベートには踏み込まず、礼儀をわきまえる。一緒に仕事をしたり、飲み会を何度もして、親しくなり、プライベートの話もするようになり、歳月を重ねることで、「さっさと結婚しろ」「バカ〜お前に言われたくないよ」という軽口も叩けるような関係になる。
だが、Facebookを見ていると「友達」承認=>現実の友達と思い込んでいるような人を見かける。僕のところにも、タメ口で「もっと努力しなきゃダメだろ?」「ちょっと痩せた方がいいよ」とかコメントを書き込む人がいた。会ったこともない人だ。それも年下だったり、映画業界ではない人。

現実でも、友達関係が深くなるには時間もかかり、何度も会わなければならない。それがネットの上で一気に「親友」という気分になっている人が結構いるのだ。が、本人はそれに気づかない。例えば承認したばかりの人が「そんなに食べるとまた太るよー」とか書き込んで来たとする。親しくない人にいうべきことではない。
ただ、良識ある人はそこで「大きなお世話だ!」というコメントは返さず「気にしているけど食べちゃうのよねー」とか、相手を傷つけない言葉を選んで返す。すると、先方はさらに勘違い。「ああ、この人。フレンドリーなんだ。ちょっと危ない突っ込みしたけど、受け止めてくれた。親しい交流をしていいんだ」と思ってしまう。
そうして、会ったこともない相手に対して「普通言わないだろう?」みたいなコメントを繰り返し書き込む。でも、そこで「いい加減にしろ! 会ったこともない奴にそんなこと言われたくない」と返事したら、相手が逆ギレして、嫌がらせを始めるかもしれない。或は「悪い奴じゃないからな〜」と考えて「そのうち止めるだろ。厳しくいうと傷付けるかもしれないから、我慢しよう」とコメントにつきあう。

それでも相手は気づかない。「友達」だと思い込んでいる。で、もうコメントが来ても返事をしない。「いいね」も押さない。そうやって、拒否していることを伝える。そうなっても相手は「仕事で忙しいんだろう」と解釈。しばらくすると、またコメントを書き込んでくる。それでも返事をしないと、ようやく気づく。てなことがある。
僕のところにも、ときどき、同業者でもなく、先輩でもない、若い人が、いろいろと指摘やアドバイスを書き込んできたことがある。悪い人ではない、応援のつもりなのだろう。が、映画作りを経験したことがないので、指摘は全て外れ。或は映画雑誌で聞きかじった情報。
「**さんはこんな努力していますよ」とか書き込んで来る。「太田監督は***を知らないようだから、***の考え方も教えてあげねば!」と親切のつもりなのだ。が、「会ったこともない年上の人にあれこれ注意する立場なのか?」とは考えない。「親切」と思いこむ。そんな心理が分かっていただけに、傷付けずに、大きなお世話をどう止めさそうか?悩んだこともある。

結構、多くの人が「人と人との距離」を計るのを苦手としているのではないか? 本来友達というのは、月日を重ね、苦労を共にし、笑ったり、泣いたり一緒にすることで絆が育つ。でも、若い頃にそんな経験をせず、友達の少ない人がいる。そこにFacebookというツールが登場したことで、「友達」が作れると感じる。同じ気持ちの人が多かったのか、あっという間に広がり定着した。
そして実体験で「友達関係」をあまり経験していない人は「申請」すれば「友達」になれると無意識に思ってしまうのではないか? 寂しい生活の中で、誰か親しい友達がほしいという思いをFacebookに投影してしまい、本当の友達ではない「友達」に対して、会ったこともないのに、親友モードで接してしまうのではないか?
でも、結局は返事がなくなり、「いいね」もくれなくなり。疎遠になってしまう。これは幼少時代にコミニュケーション能力が十分に育たなかったからだと思える。学校では「友達の作り方」は教えない。昔は放っておいても子供たちは友達を作った。けど、最近の子供たちは勉強、勉強。そしてゲームと、人とコミニュケーションする機会の少ない時代。
そんな子供たちが大人になり、Facebookに嵌った。でも、ネットの世界でもやはり本当の友達ができない。そんな悲しい現実があるような気がする。

2015年05月11日 Posted by クロエ at 09:58 │Comments(0) │MyOption
「夢見る力」シリーズ 「実力があれば採用される....というのは間違い。決め手は趣味?」

シナリオライターや小説家、或は漫画家を目指す若い人からよくアドバイスを求められる。「脚本家になりたい!」といいながら、シナリオを書いたこともない人が多いのが現実だが、努力している人もそこそはいる。助監督を続けながら、シナリオを書く努力家もいる。これまでも、それらの人たちに向けた応援文を書いたが、今回は少し違う方向で書いてみる。
ある助監督君。撮影撮影の毎日で体力的にも大変なのに、オリジナル・シナリオを書き続けている。完成したらプロデュサーに見せて「映画化したいんです」とアプローチする。が、ほとんどが却下。「そうか....まだまだ、オレの実力がないんだ。次は、誰もが映画化したくなる面白いシナリオを書こう!」と前向きにがんばっている。
が、プロデュサーのほとんどはシナリオを読めない。映画化するのはベストセラー漫画か小説。で、ないと企画会議を通せない。オリジナルを映画にしようなんてまず考えない。そんな人たちにシナリオを見せても乗ってくる訳がない。なのに彼は「オレの実力がまだまだ」と考えてしまうのが痛々しい。
同じく小説家を目指す若い人がいる。原稿が書き上がると出版社を訪ね、編集者に読んでもらう。が、こちらも何だかんだで採用されない。「実力がないから認めてもらえないんだ....」と毎回、落ち込んでいる。が、それも少し違う。編集者は映画のプロデュサーよりずっと読む力がある。「表現力が貧しい」と言われれば、それは正解。けど、出版されなくても落ち込むことはない。
これは漫画でも同じなのだが、編集者という人たちは頭のいい人たちが多く、小説や漫画をよく読んでおり勉強家。その点、映画のプロデュサーはそういう人は本当に少ない現実があるのだが、出版界はがんばっている。といって編集がダメといったら、ダメかというと、それは違う。

あの大ヒット作「リング」も当初はどこの出版社でも「???」という反応。出版されることはなかった。が、角川の名物編集者といわれる個性的な人が気に入り、出版。大ベストセラーとなった。京極夏彦さんの小説も、ある編集者が気に入って出版したが、「あの人じゃなきゃ、絶対に出さないよ」とあちこちで言われた。でも、これも大ベストセラーとなる。
つまり、編集者Aさんが「ダメ。これは出版できない」といっても、Bさんが「これは面白い。出版したい!」ということがあるのだ。もし、持ち込み原稿をAさんが読んだら、そこで終わり。たまたま、Bさんが読んだら出版!ということになる。要は編集者というのは実力ある人を選ぶのではなく、ある程度は実力がある作品で、大事なのは趣味。
だから、趣味が合う編集者と出会えるかどうか? が大きい。あの宮部みゆきさんの「魔術はささやく」だって、原稿を何ヶ月も読んでもらえず、保留のままだったと聞く。「ドラゴンボール」の鳥山明さんだって、何度も原稿持ち込みしたけどダメで、その編集者の隣席の編集者が読んで気に入り掲載、大人気になったと聞く。
シナリオライターも同じだ。オリジナルは映画化されることはまずないが、その物語テイストがプロデュサーの趣味に近ければ別の形でも、仕事が舞い込むことがある。結局は趣味! そんなことで作家はデビューしたり、消えて行ったりする。なので「オレの実力がないから....」と悩んだりするのは本質を突いていない。ダメでも「趣味が違うだけ」と自信を持とう。
そして「誰でも映画化したくなる力あるシナリオを書こう」なんて、考え方は間違い。基本は趣味なのだ。誰もが賛同する作品なんて本来ありえない。だから、「ウケる作品を書こう」とか「この路線が今は売れるから」なんて姑息なことを考えて書くのもダメということ。

自分が書きたい作品を書き、そこに趣味がにじみ出したとき、同じ指向性を持つ人が、その作品を認めてくれるのだ。もちろん、表現力があった上でのことであり、実力もないのに「そうか、趣味で書けばいいんだ」というのは間違い。実力は大切だ。
これらのことは新人作家だけの問題ではない。製品でも、食事でも、玩具でも、サービスでも、同じ。お客さんの志向と合うときに売れる。でも、「誰もがおいしいと思う料理を作ろう」とか「今、***が流行だから」という思いでは成功しない。
シナリオや小説と同じで、自分はこれが好きだ!という自分の趣味や思いがそこに反映されてなければ受け入れられないのだと思える。もっと言えば、自分は何が好きなのか? どんな思いを持っているのか? それをしっかりと把握せねばならないということ。「好き」ということ「趣味」ということ、とても大切だということ。改めて感じる。

2015年05月02日 Posted by クロエ at 14:08 │Comments(0) │MyOption
「向日葵の丘」「思い」を同じくした仲間がいるから、素晴らしい仕事ができる!

「俳優さんが演技してるとは思えない。何か本気としか思えない」
という感想をよく頂く。「太田映画に出た俳優は輝いている」というコメントもよくもらう。本当にうれしいことだが、僕自身、その理由が分かっていない。
「シナリオがいいので、俳優ががんばるのでは?」という意見もあるが、それだけでもなさそう。「いい俳優さんを選んでいるから?」とも聞くが、その俳優がいつも以上に輝いていることが多いとも言われる。
そう考えて、最近ある事実に気づいた。以前にも書いたが、僕の映画は全て僕自身がキャスティングする。あちこちから自他推薦が山ほど来るが、全て自分で決める。誰かの顔を立てて入れるとか、仲がいいから起用するということはない。プロダクションから何かもらっても、お世話になった方から強い推薦があっても受け入れない。
だが、通常はそんなことでキャスティングは決まりがち。
内閣の組閣と同じで**派からは**大臣。***派には***長官という具合に適材適所ではなく、派閥の力関係で大臣の椅子が振り分けられるとよく言われるが、映画のキャスティングもそんなことが多い。

プロデュサーの***さんが推薦する子をメインの1人に。
スポンサーのCMに出ている子を相手役に。主役の***さんと同じ事務所の俳優を5人というふうにして決まったりする。映画の「キャスティング権」は監督にあるのだが、まわりに気遣い。円滑に製作を進めるために、皆の顔を立てて役を決めるのだ。まさに組閣。
或は最初から主役が決まっていて、メインどころも全部キャスティングされてから監督が呼ばれることもある。テレビ局製作の映画でよくあるパターン。でも、そんな形で作られた作品はなぜか? 感動できないものが多く。素敵な作品が少ない。有名俳優がたくさん出ているのに、何かヘン。
理由のひとつは俳優たちの芝居が「お仕事」になっていて、
下手ではないが75点の演技しかしないからだ。なぜ、そうなるか? いろいろ理由はあるのだけど、俳優同士のコミュニケーションがある。それなりの俳優が集まれば、それぞれが気遣う。あまり自分だけ熱を入れて演じて、相手を食ってしまうのも問題。自分の演技ペースにこだわると、相手の邪魔をすることもある。だから、空気を読み。それなりの芝居をする。
ある意味で「紅白歌合戦」だ。大物アーティストが勢揃いするので、互いに気遣い。個性が発揮できない。単独のコンサートでは魅力的な人が「紅白」ではかすんでしまう。だから、大物歌手は出演を拒否したり、中継で対応したり、ゲスト的に出てすぐ帰ったりする。自身の力を100%発揮できないので一歩引いた対応で個性を守ろうとするのだ。

同じように大手の映画でも、有名俳優が勢揃いする作品。
或はひとつのプロダクションから大勢が出演していて、外部俳優の肩身が狭くなる現場も同じような環境に陥るのだ。そこで話を太田組キャスティングに戻す。
僕が選ぶ俳優さんたち。人気があるかどうか?より役にふさわしいかどうか?で選んで来た。が、それら俳優さんと現場で話している内に結構、趣味志向が近かったり、周波数が同じだったりすることが多いことに気づいた。演技志向で「いい芝居がしたい!」「命がけで演じたい!」という俳優さんがほとんど。
僕は毎回、遺作だと思って映画を作る。いい作品を作れれば死んでもいい!と思っている。そのせいか、無意識に選んだ俳優さんも遺作とは言わないが、命がけで演じるタイプだったりする。だから、僕が細かいことを説明しなくても皆、それぞれの役を把握し、自分なりに考えて最善に芝居をしてくれる。
そして、趣味志向も近い、思いも同じ。
そんな俳優さんたちが集まると、俳優同士も通じ合うところがあり、互いに「この人なら真剣にかかっても受け止めてくれる!」と感じて、遠慮なく熱い演技がする。相手ががんばれば、「私も負けてられない!」とがんばる。
おまけに僕はあれこれ注文を付けず、自由にやってもらう。だから、各自が真剣に考え、演技。現場が次第に熱くなり、誰もが100%の力で芝居をするようになる。どーも、それが「太田映画の俳優は皆、輝いている」といわれる背景ではないか?とある評論家さんと話をした。

これは僕自身が意識していなかったことなのだが、
そういうことかもしれない。そして、それが出来るのはキャスティングは全て僕自身がやっているからだと気づく。いろんな人の顔を立てて、俳優を選ぶのではないから。もし、そんな形で選んでいたら、ギャラが安いと手を抜く俳優、芝居より自分が目立つことを優先する人、プライドがやたら高い役者、等の人たちも集まってしまい、現場の空気が悪くなってしまう。
でも、僕自身が全てを選ぶことで、気がつくと、そんな俳優は1人もいない。その理由は「感じるものがあるか?」で選ぶからだろう。感じるものあるというのは、僕が命がけで映画作りをするように、その俳優も命がけで芝居をする人だということで「感じる」のだ。そんな俳優が集まるから皆、気兼ねなく素晴らしい芝居をしてくれる。
実はスタッフも同じ発想でお願いしているのだけど、
スタッフ、キャスト共にそんな熱い人たちが集まったので、毎回、現場は盛り上がり、熱くなり、評価される映画が出来るのだと思える。
映画は監督1人ではできない。「思い」を共有できる素晴らしい「仲間」が集まってこそ。素晴らしい作品になる。これは映画でなくても同じだろう。同じ思いを持った仲間がいてこそ、素晴らしい仕事ができる。そんなことを感じる。

2015年04月14日 Posted by クロエ at 15:55 │Comments(0) │MyOption
「向日葵の丘」「太田映画の俳優はなぜ輝くか?」というコラムに書かれた答え。

ある映画評論家さんが「向日葵の丘」パンフレットに、そんなタイトルの文章を書いてくれるらしい。
確かに「太田監督の映画に出た若手俳優は皆、素晴らしい!」とよく言ってもらえる。最初は「俳優の**ちゃんが素晴らしい!」と言われるのだが、次の映画も、次の映画も若手が輝いている。で、こう言われるようになる。
「これは俳優が魅力的なのはもちろん。そんな新人を選ぶキャスティングがいいだ! 太田監督は有能な若手を選ぶのがうまい!」
恐縮してしまうが、うれしい話だ。以前にも書いたが、僕が俳優を選ぶときは事務所が大手で力があるとか、すでにブレイクしていて人気があるからでは選ばない。プロデュサーが***を使え、と圧力をかけても承諾しない。自分の目で見て本当に魅力的な子を選んで来た。その結果、その子たちが輝き、ブレイクして行った訳であり、僕が特別見る目があるというより、業界のブランドや横やりで決めないだけのことなのだ。が、こう言う人たちがいる。
「若手はとっても魅力的だ。でも、他の俳優も素晴らしい。テレビでよく見る***さんも、いつもと全然違う!」「***さんがあんないい役者だと思わなかった」
そんな声もよく聞く。毎回、出演者の評判はいい。映画評論家さんも同じことを考えたという。「これはキャスティングの問題だけでなく、太田映画に出た俳優の多くが輝いているということ。何か理由があるはずだ...」僕の映画を全て観てくれている友人も、似たようなことを考えたという。
「理由はきっと、太田さんが書くシナリオにあるんだ。素敵な物語なので、俳優さんもいつも以上に張り切って演じるのではないか?」
しかし、映画評論家さんはベテラン刑事のように首を捻る。「それだけだろうか? 他の映画ではシナリオは素晴らしいのに演技がダメな俳優もたくさんいる。他に何か理由があるはずだ。例えば撮影現場で演出とか? 事前の打ち合わせとか...」彼はそう考えて、出演者たちにそのことを訊いたという。だが、皆口を揃えてこういう。
「事前打ち合わせはしていません。現場でも監督はあれこれ言わないですよ」
そこで刑事さん。いや、評論家さんは行き詰まってしまった。打ち合わせもなし。現場でも何も言わないのに、なぜ、俳優たちが輝くのか? 名演技をするというより、役柄そのもの。登場人物の1人に成り切っている。そんなことが何の理由もなしに、起こりえるはずがない。理由は何だ? でも、答えが分からない。ということで、直接、僕に電話がかかってきたのだ。
でも、俳優たちの言う通り。僕は俳優たちと演技プランの打ち合わせはしない。「好きにやってほしい」というだけ。現場でもよほどのことがないと、注意したり、あーしろ、こーしろとは言わない。が、最終的に俳優たちは素晴らしい芝居をしてくれる。それを評論家さんに指摘されて、「確かに...なぜだろう?」と思ってしまった。
その謎が今回の「向日葵の丘」で解けた。僕が当たり前だと思っていたこと。尊敬する巨匠たちの方法論をあちこちで聞き、学び実践したこともあるが、そんなことが大きな効果を発揮していたこと。初めて痛感することになった。
映画というのはやはり深く、複雑であり、これをすれば名作になるという手法はないことも同時に感じた。さ、その理由とは何か? 答えはパンフレットに掲載されるが、その前部分の経緯をいずれ紹介したい。

2015年04月10日 Posted by クロエ at 19:18 │Comments(0) │MyOption
太田映画式、ロケ地を魅力的に描く方法?

僕の映画は毎回「親子に伝える大切なこと」がテーマだ。最近はさらに一歩進んで「幸せって何だろう?」も主題となってきた。それと同時に、僕の映画は「古里映画」とも言われる。師匠である大林宣彦監督が尾道シリーズを撮ったように、僕も都会ではなく、地方を舞台にした映画を撮り続けている。
和歌山、浜松、湖西、島田と、皆、有名な観光地ではないが、昔懐かしい風景のある素敵な町だ。映画を観た人は必ず「この町を訪れてみたい!」といい。そして、誰もがそこが自分の故郷であるような郷愁を覚えるという。
これはとてもうれしい話だが、町を魅力的に描くというのはなかなか大変なことで、俳優を魅力的に描くのと同じ愛と努力が必要だ。というのも、有名な観光地を舞台に「***市ロケの映画」というふれこみで作られた映画がときどきある。それを観ると、確かに街を美しくは撮影しているが、何か観光地の絵はがきのように「けど..」という気持ちになる。
そう観光絵はがきというは、美しいが心がない。伝わらない。魅力を感じないことが多くはないか? それはカメラマンがその街を愛していないからだと思える。2泊3日で撮影に来て、ロケ場所にのみ訪れ、撮影が終わればさっさと帰る。そんな仕事の仕方なので、技術で風景を美しく撮れても、愛が籠っていないのである。
では、どうすれば愛が籠るのか? は何度も書いたが、まず、スタッフがその街を好きになること。何度も訪れて、その街を知ること。街の人と触れ合うこと。地元の名産を食べること。そうやって街を好きになってこそ、その街の魅力を理解し、愛が籠った映像が撮れるようになるのだ。いつもスタッフだけでなく、キャストにもそのことを伝え、街を体験してもらう。
費用も、時間も、手間をかかるが、そうして撮影に臨むと、街が微笑んでくれて、いつも見せない素敵な顔を見せてくれる。そのせいか、映画の舞台となる街はいつも評判よく、「ぜひ、一度訪れたい」と言われる。が、ときどき、その地元から逆行する要望が出ることがある。一部の人だが、せっかく地元をPRする機会なのに、それを妨げることをするのか?と思うのだが、また、その話も紹介する。

2015年04月10日 Posted by クロエ at 19:14 │Comments(0) │MyOption
「向日葵の丘」映画の成功はキャストだけでなく、スタッフ選びも大きい!

後輩の映画監督から相談を受けた。撮影現場が非常に混乱してうまく行かなかったのだが、理由が分からないという。スタッフ同士が議論になったり、喧嘩したり、ギクシャク。まとまらずに、それぞれが勝手なことを始めたというのだ。
そう聞くと普通なら「相性が悪いスタッフが多かったんだね?」とか「ギャラが安いのでイライラしてたんじゃないの?」とか言われそうだが、後輩はそういうことではないというのだ。で、いろいろと訊いてみると、ああ、なるほど、それはうまく行かないな.....ということが分かった。
まず、後輩が監督したのは低予算映画。それをドキュメンタリータッチで撮影しようとしたという。手持ちカメラを多様。多少のブレがあっても、台詞が聞き取れなくてもOK。それよりリアリティを重視。あえていえば、アメリカのテレビドラマ「24」をさらにエスカレートさせ、「これはドキュメンタリーじゃないの?!」と思えるほどのリアリティある映画をめざした。
次にスタッフを訊くと「カメラは***さん。照明は***さん、助監督は***君」と名前を上げてくれた。その段階で「ワトスン君。答えは簡単さ!」といいたかった。もちろん「AさんとBさんは犬猿の仲なんだよ。うまく行くはずがないさ」なんて真相ではない。映画作りの難しさがそこに現れていた。
まず、カメラのAさん。この人はドラマでもドキュメンタリーでも出来る人。だが、照明のBさんはバリバリの映画人。結構ベテラン。そして、助監督のCさん。この人はテレビドラマを専門にやっている。もう、これだけで答えは出た。
後輩監督の意図を理解しているのはカメラマンのBさんだけだからだ。作品の方向性はドラマだがドキュメンタリータッチ。だが、照明のBさんはバリバリの映画人。こだわった映像で重厚な物語を作って来た人。それに対して助監督のCさん。テレビの仕事が多いので、とにかく早く撮影する。クオリティは多少低くて、予定通りにクランクアップすることを重用視。

この中に後輩が意図するドキュメンタリータッチのドラマを理解しているはカメラマンだけなのだ。例えば手持ちカメラがグラグラ揺れとする。通常の映画ではNGだが、ドキュメンタリーならOK。そして映画の撮影なら最初にピントを合わせてピンぼけを出ないようにするが、ドキュメンタリーならOK。それをあえてドラマでやろうというのが意図なのに、映画の照明部も、テレビ専門の助監督も「それはおかしい!」と受け入れなかったのだ。
その上、照明部はドキュメンタリーではありえない、おしゃれなライティングをするし、演出部は「役者の顔をしっかり映さないと!」とテレビドラマの定義を持ち出す。どちらもドメキュメンタリーでやったらおかしなことになる。つまり、監督の意図をスタッフのほとんどが理解せず。また、テレビ系、映画系のスタッフもそれぞれに価値観が違い、ぶつかったということなのだ。
後輩、曰く「作品意図の説明を聞き、皆、分かった!といってたんですよ」そして一般の人から見ても映画も、テレビも同じ。仲良く出来るはず、画面サイズが違うだけ。ドキュメンタリーもほぼ同じ。という認識だろう。が、これらは全く違う。似て非なる物。あえていうと宗教と同じ。知らない人が見れば宗教なんて皆、神がいて、その教えを信じるものだと思いがちだが、そのささやかな違いで海外では戦争まで起きている。映画やテレビもまた同じ。
それぞれが宗教だと思えば理解しやすい。例えば映画では「監督」が絶対的存在だが、テレビは「プロデュサー」、CMでは「スポンサー」ドキュメンタリーもまた「監督」だろう。つまり、映画のスタッフは「監督」のためにがんばるが、テレビは「プロデュサー」だ。CMは「スポンサー」第一。
僕も以前、CMのスタッフとドキュメンタリー作品を作ったが、何かあると「だったら、まずスポンサーに報告して承認を得ないと!」言い出す。何かにつけそれ。いい加減うんざりした。ドキュメンタリーはスポンサーのために作るものではないのだ。同じく、後輩の映画でも、テレビ系は監督よりもプロデュサーにへつらい。監督をないがしろにしていたらしい。
さらに、それぞれの方法論が違い、議論になり、言い争いになる。でも、それは最初から見えていることだ。後輩は事前に説明したというが、何十年も実践してきた方法論を人は簡単に変えることはできないのだ。もし、ドキュメンタリータッチを実践するなら、テレビや映画スタッフではなく、ドキュメンタリーのスタッフでドラマを作るべき。
或は、その種の発想を理解するスタッフを選ぶべき。名前を聞くだけで、「その人にドキュメンタリーは無理!」というタイプをスタッフにした段階で失敗は見えている。よくキャスティングが成功すれば、映画の70%は成功だと言われるが、スタッフも同じ。そこで間違った人を呼ぶと、テロリストを乗せて船出するのと同じになってしまう。
映画スタッフのみならず、新入社員でも、何でも、人選というのは本当にむずかしい。が、それがうまく行けば大きな成功が掴めるのだが。