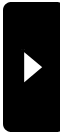「向日葵の丘」監督日記 映画監督は冷静ではいけない? 感情的でないと駄目?

「監督〜ちゃんと冷静に仕事してくださいよ〜」とメールをくれたスタッフがいる。このFBで「毎日、泣きながら編集している」と書いたのを読んだようだ。彼が思うのは「監督たるもの感情に流されず、冷静に客観的に編集をするべきだ!」という意見なのだろう。
基本的には合っている。「この女優さん。好きだから長めにカット使っちゃおう〜」と、不必要に個人的な趣味で編集するのは駄目。このカット撮るのに撮影部さん苦労したのに、全く使わないと申し訳ないから残そう」とかいうのも駄目。だが、映画というのは、そもそも感情に訴えかけるもの。それを客観的に冷静になって作業しているだけではいけない。
そもそも、監督というのは観客の代表であり、一番最初に俳優の演技を見て、映像になったものも見る。そこでどう感じるか? 感動するのか? 笑うのか? 泣くのか? それが重要なのだ。どう感じたか?で演出や撮影方法が決まる。
逆に言えば、感動的な演技を見て、冷静に客観的に捉えるというのは、その芝居に感動できないということ。それは冷静なのではなく、感動できる感性がないのではないのだろう。だから、観客の代表であり、最初の観客である監督はある意味で冷静で客観的ではいけない。観客と同じ感性の目を持ってなければならない。
黒澤明監督の「静かなる決闘」の撮影中。主演の三船敏郎の演技にカメラマンは感動したという。あまりの感動に手が震えるので、カメラが揺れてはいけないと、手を離して撮影を続けた。そのとき「黒澤監督はどんな表情で見ているのか?」と思い、振り向くと、ボロボロと涙を流しながら三船の芝居を見ていたという。
また、「男はつらいよ」シリーズの撮影。本番中に渥美清さんのアドリブでスタッフまで笑ってしまい、NGが出ることがよくある。俳優でない人の笑い声が録音されるのはまずい。で、そんなとき大笑いして一番NGを出すのが山田洋次監督。それらのエピソードを聞くと、冷静で客観的というより、監督業は一番、感受性が強く、一番笑って、一番泣くタイプの人ではないか?と思える。
なのに、昔から映画界では「監督は冷静沈着。客観的に芝居を見なければ駄目だ」という人が多い。確かに、現場で取り乱したり、泣き崩れたりするのはマズい。でも、やはり、巨匠たちのエピソードを聞いていると「冷静」「客観的」より「感情的」な人が多い、少なくても編集作業ではその資質が必要だと思える。
自分で監督した作品は何度も映画館へ行き、どこで客が笑い、どこで泣くか? どこでどんなリアクションをするか必ず確認する。東京だけではなく、行ける限り全国の映画館へ行く。そこで客席には座らず、壁ぎわに立ち。スクリーンと客席を交互に見ながら、客の反応を確かめる。
客層も、若い人、学生、子供、男性、女性、お年寄りといろんな人を見る。面白いことに、どの県でも、どこ劇場でも、皆、同じシーンで笑い、同じシーンで泣く。これは国内だけでなく海外で上映しても同じ。そして、それら泣けるシーンと笑えるシーンは、皆、編集時に僕自身が泣き、笑った場面である。
つまり、自分が泣けないものは観客も泣けない。自分が笑える芝居はお客さんも笑うということ。自分は泣けないのに、或いは笑えないのに「観客を泣かそう」「笑わそう」と考えて、編集すると駄目。それが分かってから、編集しているときに、泣けるか?どうか? がかなり大事なポイントだと考える。で、今回、何シーンで泣けたかな? 果たして劇場ではどうか? 楽しみである。

2014年08月31日 Posted by クロエ at 19:51 │Comments(0) │編集作業
「向日葵の丘」監督日記 やっと編集が終わったと思ったのに!
.
編集した映像をまたDVDにして確認。
もう、問題点はないと思ったのに、直さねばならない箇所を発見。
メモを取りながら見ると何カ所も!
そういっている内にエンドロールが送られて来た。
よし! これをつければ完尺がでる。
今日は完成版を音楽家さんに送ったら、
3ヶ月ぶりののんびりできると思ったが、
そうも行かないようだ。


編集した映像をまたDVDにして確認。
もう、問題点はないと思ったのに、直さねばならない箇所を発見。
メモを取りながら見ると何カ所も!
そういっている内にエンドロールが送られて来た。
よし! これをつければ完尺がでる。
今日は完成版を音楽家さんに送ったら、
3ヶ月ぶりののんびりできると思ったが、
そうも行かないようだ。

2014年08月29日 Posted by クロエ at 19:05 │Comments(0) │編集作業
映画の中にもう一本の物語ー黒澤明監督の「赤ひげ」と「向日葵の丘」

もう一度、正確にタイムを計ると、
前半が1時間9分50秒。
後半が1時間5分21秒。
合計、2時間15分11秒。
「あと、11秒くらい、がんばって切ればいいのに」という人もいるだろうが、水泳のタイムではない。短ければいいというものではなく。物語にとって本当に必要な時間と、観客が映画を観ていられる体力とを考えて設定した時間にどこまで近づけるか?が大切。その意味では目標達成である。
まあ、でも、最初は2時間45分もあったのだから凄い。それを30分も短くした。といっても、まるまるカットしたシーンはそう多くはない。1シーンだけある俳優に問題があり、全く使わなかったが、それを入れても*****、*****、と短い場面が3つくらいだ。
ほとんどのカットは各シーンの頭と最後。
そしてそれぞれにカットを1秒、2秒とカットして行った。だからこそ、30分切っても物語は繋がるし、説明不足にはなっていない。そう書くと業界の友人などは「だったら、もう少しがんばって2時間にすれば、いろんな面でメリットが多いのに!」と必ずいうが、それは駄目だ。
今回の映画。というより、僕の作品は基本的に長い。なぜか?というと、実は中身が通常の映画の2本分あるからだ。時間ではない物語がだ。分かりやすくいうと、本来なら2本の映画として作れる分量を1本の映画として完成させている。近い形でいうと黒澤明監督の「赤ひげ」
あの映画は2本どころか、4、5本分の物語の分量がある
(原作は短編集だし)中でも、山崎努さん演じる佐八のエピソード(地震で恋人と生別れになる話)はそのまま1本の映画にできるだけの中身と分量。本来の主人公は保本(加山雄三)なのに、あのパートは完全に佐八が主人公。保本は登場しない。まさに、山崎努・主演の物語となっていた。
通常、あの種の話を持ち込むと映画内映画になってしまい、上映時間が長くなる(実際「赤ひげ」はそうなった)だから、台詞で説明したり、フラッシュバックで回想させて時間をかけないようにする。それが多くの映画の手法。でも、それでは、あの佐八の悲しみや葛藤を伝えることはむずかしい。あそこまで延々と描いているからこそ、体感できる。
だからこそ、加山雄三演じる保本が心変わりする場面でも
納得いくのである。それと同じ手法を使ったのが僕の監督2作目「青い青い空」。熱血教師・八代先生(波岡一喜)の過去。彼とオカンとの物語がかなりの時間を割いて描いた。だからこそ、生徒たちが真剣になって行く心境にも共感し、最後はもう応援せずにはいられなくなる。それは「赤ひげ」から学んだ手法。
なかなか、むずかしく。手間も時間もかかるので、あまり実践する人はいないが、お手軽テレビドラマ(回想やうわさ話で人物を簡単に紹介する)方法論では伝えられないものがある。今回も、それに近い手法を使った。だから、2本分の物語が混在する。「青」は生徒たちと八代先生。さて、今回は? ヒントは「GF2」ー
その手法がとてもうまく機能していて、下手すると今回の物語は「青い青い空」路線の第二弾と思われそうなところが、それを凌ぐものが出来きそうだ。ともあれ、それを2時間15分でまとめられたのは、自分でビックリ。
それが出来たのは多くの俳優が役やテーマを理解し、魂を削る芝居をしてくれたからである。と、長々書いたが、本日は書き出し大会である

2014年08月28日 Posted by クロエ at 13:07 │Comments(0) │編集作業
「向日葵の丘」監督日記 前後編を続けて見る!

映画「向日葵の丘」編集最終日。それぞれに1時間少々ある前後編を一気に見た。これまでは、前半を見て、1日がかりで直し、その翌日に後半を書き出して観て....という形だったが、今回は初めて前半後半を一気に見た。映画館で見るのと同じ状態だ。休憩はない。
個々のシーンの印象や感想はすでに書いたが、やはり、前半は楽しく、笑いながら見れる。それが後半。もうオープニングから悲しい。そこからは胸締め付けられ、涙の場面が連続。そしてクライマックスは感動の涙の連続。まだ、涙が溢れているのに次のシーンでまた涙が溢れる。
観客の視点で観ながらも、同時に監督して問題点がないか? 分かりづらい部分はないか? 短縮を考えながらも、もう少ししっかりと映像を見せないと伝わらないのでは?という観点からも観る。忘れないようにメモを取ると、以下の写真のようにA4ペーパー4枚にもなった。
そのほとんどは***のアップ。1秒長いとか。そんなことばかりなのだが、いくら直しても直す部分は出て来るものだ。パソコン上で観るのと、大型モニターで観るのはやはり違う。これが映画館で観ると、また別の粗が見つかったりするので怖い。
そして上映時間。2時間15分を目指して、あと83秒ほど長いのだが、全然問題ないという感じ。もう少し長くても大丈夫だろう。カットが短く、分かりづらい部分があるほど。調子に乗って切りすぎたところもある。だが、カットしたことで前半はスピーディになって見やすくなった。
あと自分が脚本を書き、監督した作品というのは、よ〜く内容を知っているので、実は観ていて退屈しやすいということがある。最初は「うまく行っているかな?」とドキドキしながら観るが、繰り返し観ていると感動も薄らいで来て、全編を通して観るのが億劫になるもの。なのに、今回も退屈せず、2時間15分。一気に観てしまえた。初めて見る人ならもう全然問題なく、楽しく、そしておおいに涙するはず。
さて、このあとはmemoに従い、直し編集。そして、いよいよ、本日中に編集終了だ。

2014年08月28日 Posted by クロエ at 13:04 │Comments(0) │監督日記
「向日葵の丘」監督日記 いよいよ最終日!本日で長さは決着。

3ヶ月に渡る編集作業。いよいよ、本日が最終日。小さな直しはまだ先もできるが本日で尺(長さ)を決めて、それはもう動かせない。昨日までの作業でタイムを出してみた。
前半1時間10分44秒
後半1時間5分39秒
これまでと同じように、時間と分までの計算なら前後編ともに目標達成! 2時間15分になった。が、秒の単位を足すと、まだ83秒長い。本日1日、格闘してみて、無理はせず、その時間を最終決定にする。
そもそもの話をするが、テレビドラマの場合は1時間ものだと、ドラマ部分は正味43分くらい。それは長くも短くもできない。秒単位まで計算して仕上げる。だから、「今回のエピソードは何か回想シーンが多かったなあ」というときは、尺が足りなくて、過去の映像を使い時間合わせをしたということが多い。
それに対して映画は基本的な決まりはない。だから、1時間10分くらいの映画から、6時間にも及ぶ大作まである。だが、お客さんの気力、体力を考えると、1時間45分から2時間。そのくらいが見やすい長さなのだ。
あと、長くなると映画館側が嫌がる。2時間の映画なら1日4回上映できるが、4時間なら2回になる。入場料は同じなので、収入が半減する。だから、映画館側へのアピールを考えるなら2時間以内にするのがベスト。といって、短くすることで作品のクオリティを下げるなら本末転倒だ。
今回の「向日葵の丘」シナリオ上で計算すると、1p1分と計算する。135pなので2時間15分。でも、荒編集してみると3時間あった。それをさらに詰めると2時間45分。ま、そこがスタート。編集を始めた。
シナリオで読むと必要でも、映像にすると、そこまで説明しなくても分かるというシーンも出てくる。テンポやリズムは大事なので、長いシーンは短くする。そして、俳優さんの演技も期待はずれの人は、やはり短くする。今回もほとんどの俳優は素晴らしかったが、やはり力足りない方も少しいた。
決して手抜きした訳ではないのだろうが、ときとして俳優は100%の力を出さず、「お仕事」をすることがある。或いはギャラに相当するレベルで済ませる。テレビドラマを見ていると、そういう方がときどきいる。が、それでは困る。だから、こちらも「やる気」にさせる努力をするのだが、結局、それなりで終わる俳優もいる。或いは期待したのに、そこまでの実力がなく、プロとは言えない芝居しかできない新人もいる。
そんな俳優のシーン。全部をカットすると、物語が繋がらなくなるが、できる限りカットして、目立たないようにする。本来なら別の俳優でもう一度撮影したいくらいだが、それには高額の予算がかかる。また、その俳優を選んだのは僕だ。本当に実力を見抜けなかった自分自身の責任。
でも、芝居が落第点の場合は躊躇なくカットできるが、いい芝居なのにいろんな理由でカットせねばならないときは辛い。先にも書いたが、物語のスピードやテンポは重要だ。その中でどうしても切られねばならない台詞や芝居も出てくる。そんなときは本当に苦しい。その場面だけ見れば、あった方が面白くても全体から見たとき、その場面で物語が停滞することになるのだ。
様々な理由や価値観で、編集。結局、まるまるカットしたのは、3シーンくらい。「それが分かってれば撮らなければいいのに!」と言われそうだが、撮ったからこそ、それが判断できたし、「せっかく苦労して撮ったんだから」と残すと、それは映画全体を駄目にすること。「あの日。本当に大変だったし、**さんはがんばったからなあ」と残したくなる場面もあるが、冷酷さが必要だったりする。

2014年08月28日 Posted by クロエ at 13:00 │Comments(0) │編集作業
「向日葵の丘」学校でいくら学んでも夢は掴めない?ー映画監督になる方法

高校時代。将来、映画監督という仕事をしたいと思った。いや、ちょっと違う。映画監督になりたかったのではなく、映画が作りたかったのだ。シナリオを書き、撮影をして、編集をして、観客が喜ぶ作品を作る。それができる仕事というのが「映画監督」という仕事だった。
が、1970年代すでに、大手映画会社では新入社員の募集をしていなかった。昔は、映画会社の試験にパスし、そこで助監督をしながら経験を積み、監督になるというのが王道だった。あの黒沢明監督だってそうだ。なのに、当時もう映画産業は斜陽で、映画会社はテレビドラマの下請け制作等で食いつなぐ状態。すでに自社専属の監督や脚本家というのはおらず。ほとんどのスタッフがフリーであった。
高校生の僕は、どうすれば日本で映画監督になれるのか? 調べてみた。それで先の黒沢監督ら大監督たちが映画会社の社員として、入社。監督となったことが分かる。社員募集がなくなってからは、それ以前に映画界に入り、助監督を勤めて来た人たちが監督になるケースが多かった。
ただ、それは若い人たちには当てはまらないケース。さらに調べた。CMディレクターをやっていた人が映画を作り、その後、映画監督になるという形も見つける。大林宣彦監督だ。百恵友和コンビのグリコのCM。ソフィアローレンのラッタタタ。Cブロンソンの「ん〜マンダム」とヒット作を撮ったあと、「HOUSE」で映画監督デビューしている。
「映画監督になるには、CM界で成功してからでないと今の時代は駄目か?」と思えたり。さらにハリウッド監督についても、調べた。「アニマルハウス」のジョンランディス監督は映画会社でメールボーイをしていた。コッポラは学生時代からロジャーコーマンのスタジオでアルバイト(Jキャメロンも同じ)ルーカスは大学時代に知り合ったコッポラの助監督からスタート。
それら多くがロサンゼルスのUSCという大学の映画科で学んだ者が多いことも分かる。そんなことがあって、のちのち僕もUSCを目指すことになるのだが、それはまだ先の話。一番興味を引いたのがスピルバーグ。大学時代にユニバーサル撮影所に忍び込み。そこで空き部屋を勝手にオフィスにして、「監査役」という名札を作り、スタジオ内を見学してまわっていた。
それがバレて、当時の社長、シド・シャインバーグに呼びつけられて「何でそんなことをした?」と訊かれる。スピルバーグは答える「映画監督になりたかったんです...」普通なら、追い出されて終わりだが、社長は2万ドル(だったと思う)で映画を撮ってみろ!といったのである。それで作ったのが映画「アンブリン」(のちにスピルバーグの会社名ともなる)その出来に感心した社長は彼と監督契約を結ぶ。そして「刑事コロンボ」の「構想の死角」日本では劇場公開された「激突」を監督。その後、メガヒットを連発するのだ。
調べてみると、それぞれが面白い。で、気づいたのは同じパターンで監督になった人はいないということ。それぞれが考え、努力して、夢を掴もうとしていた。「じゃあ、僕の場合はどうすればいい?」と考えた。そのあとに2つのチャンス。8ミリ映画ブームとUSC留学。しかし、そこではまだ夢の実現には至らない。さらに3回目の戦いでリーチをかけるのだが、それはまた別の機会に。要は夢を掴むのにマニュアルはないということだ。
なのに、先日も書いたが映画学校に通う今の生徒たち。卒業すれば監督や脚本家になれると思っている子たちが多い。講師の先生から「卒業しても何の意味もない。学校来るよりパチンコ屋でバイトしろ」と言われても、ピンと来ない。まじめに毎日の授業に出て、宿題をこなす。
彼らは日本の教育システムにどっぷり浸かり、発想を凝り固められてしまったのだ。高校受験=>大学受験=>就職試験=>会社員=>定年という日本人のほとんどが歩むコース、それ以外の方法論というのを考えることができない。だから、映画監督になりたければ、映画の専門学校に通う。卒業しても就職試験?はないのに、学校に通う以上の努力をしない。
映画作りはある種、芸術。サラリーマンとは違う。ただ、思うのはカタギの世界も映画界と同様に混沌として来たということ。もはや、入社しても定年まで安泰ではない。社員になることすら難しい時代だ。黙っていたらブラック企業で過労死するまで働かされる。どんなに働いてもまともな生活ができないこともある。映画監督になるには、様々な知恵を絞り、人とは違う方法で自分をアピールしなければならないが、現在においてカタギの仕事も同じ構図になっている。
年老いた人たちから押し付けられた古い価値観に従い、ただ学校に行くだけでは潰れていくしかない。何事においても絶対的な方法論はもうないんだ。自分なりの方法を探すこと。模索することが、夢を掴むこと、生き残ることに繋がるのではないか?

2014年08月28日 Posted by クロエ at 12:57 │Comments(0) │監督日記
「向日葵の丘」「夢見る力」シリーズ シナリオ作家になりたい人は、近道より遠回りが大事?

まだ、データの書き出しが終わらない。もう1本記事を書く。シナリオライターの話を書いたので、自身の体験を綴っててみる。僕が一番最初にシナリオを書いたのは高校時代。「キネマ旬報」に掲載されていたシナリオを見よう見まねで、オリジナルの作品を書いた。在学中に数本。とても人に見せられる内容ではない。
その後、映画学校に通ったが、あまりに退屈なので登校拒否? 自主映画を始めた。そのシナリオは自身で書いたので、毎年1本は書いていた。それから5年。自主映画をしていた仲間の何人かはプロデビュー。監督や脚本家になる。が、いろいろと感じることがあり、僕は自主映画をやめ。プロの世界にも進まず(実は業界の仕事を少ししていたのだが)アメリカ留学を決意した。23歳だった。
一番の理由は20歳やそこらの経験で、物語を作り続けることができないと思えたことだ。もし、プロになれても25歳から毎年監督したら、70歳で死ぬとして45本。3年に1本監督するとしても15本。そんなたくさんの物語を作ることができるのだろうか?
もし、監督するだけなら、良い脚本を探して映画化することもできる。が、僕は自身で書いた物語を映画にしたかった。その意味で良い脚本が書けなければ監督業を続けられない。良い脚本を書き続けるためには何が必要か? たくさん本を読むこと? 映画をたくさん見ること? いや、僕は自身がいろんなことを経験することだと考えた。
ただ、だからといって、漁師を2年。農家を2年。と仕事をしていると、豊富な経験はできるが、それでは監督できる環境に繋がらない。映画に繋がる環境にいて、それでいて業界以外の経験ができる場所が大事と考えた。それが留学だった。ロサンゼルスにある南カルフォルニア大学の映画科を目指して渡米。英語コースで勉強を始めた。そして6年。この辺のことは何度も書いたし「スクリーン」誌でも連載させてもらった。
しかし、アメリカの映画科で勉強したからと、帰国してすぐに仕事ができる訳ではない。むしろ「だから何?」という対応だった。そこからまずシナリオライターになろうと、またシナリオを書き出す。正午からレンタルビデオ屋。夕方から居酒屋でアルバイト。夜中に帰宅。そこから朝までシナリオを書く。そんな生活を続けた。何度も倒れそうになった。
その後、演劇学校で教えたり、雑誌のライターを始めたりして、生活体系は変わるが、シナリオを書き続けた。結局、デビューまでに5年! 20本以上のシナリオを書き、1本も映像化されていない。しかし、これも望んだことだ。23歳から5年がんばっていれば28歳でデビューできたかもしれない。でも、そんな奴は他にいるだろう。だから、それにプラスして6年のLA生活がある。
が、本当にそれは意味があったのか? 長らく考えた。帰国したとき、何人もの友人はすでに監督デビュー、脚本家デビューしており。「お前もあのまま日本でがんばっていればVシネマくらい監督できたかもなあ」と言われた。でも、それでは長続きしないので、遠回りしたのだ。それに意味があったこと。感じるのはごく最近である。
デビュー作「ストロベリーフィールズ」は10代の作品の延長にあった。けど、「朝日のあたる家」あたりからは、そうではないものが出て来た。今回の「向日葵の丘」は特にそうだ。あのまま、20歳前後でデビューできていたら作れなかった映画だと思える。毎回、オリジナルシナリオを書いていて感じること。物語は人生の切り売りだということ。机の上で考えたストーリーでは観客は感動してくれない。
自身が背負う業。見つめるしかなかった悲しい現実。答えの出せない苦しみを描くことで、観客は胸打たれること。痛感。だったら、何もアメリカ行かなくてもよかったんじゃない? と言われそうだが、ま、何かの役に立っているはずだ。本を読むだけ、映画を見るだけで、物語は作れない。物語は人生の切り売りだ。カードはたくさんあった方が長く続けられるはずだ。

2014年08月28日 Posted by クロエ at 12:55 │Comments(0) │監督日記
「向日葵の丘」脚本家デビューには最低5年かかる?スタートは30歳過ぎ。こちらも過酷な仕事。

なかなか、データの書き出しが終わらないので、もう1本記事を書く。22歳までにブレイクしないと契約更新できない女優業とは反対に、30歳を超えないと仕事をスタートできない人たちの話だ。
監督した映画が公開になるとき、僕は独自に宣伝活動をする。制作会社が本当に何もしないところが多いので、自分なりに動かねばならないのだ。そんなとき、よくお世話になったのが、映画学校で教える友人たち。彼らは脚本家であり、監督でもあるのだけど、副業で学校でも教えている。そのクラスにいって、映画の宣伝をさせてもらう。
ま、「笑っていいとも」のテレフォンショッキングのコーナーのようなものだと思ってほしい。学校側にはゲストを呼んで撮影現場の話をしてもらうという名目なので、教室では学べないそんな話もしつつ、映画の宣伝をさせてもらう。昨年、お邪魔した学校の生徒は皆、高校を卒業して、脚本家を目指すべく都内のその学校で学んでいる。友人の講師もプロで現役のシナリオライターだ。
そして毎回驚くことがある。ほとんどの生徒が学校を卒業すれば、プロになれると思っていること。この種の専門学校はシナリオの書き方を教えてくれるだけ。自分が書いたものを講師が指導はしてくれるが、それでプロになれる訳ではない。が、彼らは特に足掻く様子もなく、高校時代の延長のような感じで授業を受けていた。
講師の友人は型破りで「こんな学校は早く辞めて、パチンコ屋で働いた方が勉強になる」というが、本当にその通りだ。シナリオの書き方は学べるが、脚本家なんて教わって成れるものではない。そして、書く中身。高校を出て専門学校に通う経験しかしてない子たちが書けるものはまだないのだ。
なので、いつもそんな話をする。物語というと、あれこれ想像して書くものだと思いがちだが、実は違う。そうやってかけないこともないが、それでは読んでも感じるものがない。自分なりにいろんな経験をし、学び、蓄積し、分析し、見つめて、それが自分のものになり。物語として書くことができる。
だから、友人のいうようにパチンコ屋で働いた方がいろんな客を見ることができるし、いろんな人生と関わりあい、経験値が上がるのだ。が、生徒の多くは普通に高校生活を送り、映画ファンで、専門学校に来ている。何の経験もなく、これまでに見た映画の寄せ集めのようなシナリオしか書けない。それは仕方がないことなので、厳しくは言わないが、大切なのはこれ。「学校を出ても脚本家にはなれない!」
それどころか、その後、どんなにがんばってもプロになるには5年はかかるということ。それまでアルバイトをし、貧しい生活の中で、金にはならないシナリオを書き続けながら営業も続けることができるか?が問題なのだ。友人の講師も毎回、同じことをいっているらしいが、生徒たちにはどうもピンと来ないようだ。大学を出て、仕事を探し、会社員になる。というパターンでしか想像できないようで、募集されない仕事というのが、どんなものか?分からないようである。
「脚本家、募集」なんて広告は出ないし、映画会社も告知しない。働きながらシナリオ大賞に応募するくらいしか考えつかない。どうすればいいのか? これをすればライターになれる!という方法はない。以前、このFBにも書いたが大手映画会社はシナリオを持ち込んでも読んではくれない。「そのようなことは致しておりません」と返事する。が、「絶対になる!」と決めて、努力を続ければ、どんな職業にでもなれるものだと、僕は信じる。
その経緯のことはまた別の機会に書きたいが、それでも最低でも5年はかかる。講師をする友人に訊いたら、大学を卒業。田舎から出てきて、シナリオライターになり、初ギャラをもらうまでに5年かかったという。30歳を超えていたという。僕もアメリカから帰国して、ほぼ5年。31歳だった。もっとかかった友人もいる。その間、耐え続けられるか? それも5年我慢すればいいのではなく、その間戦いが続く、生活のための仕事をした上に、シナリオを書き続けないならない。でないと実力も着かない。
そして、1本目を書いたからと2本、3本と依頼が来る訳ではない。そして、勉強し、いろんなことを吸収し続けないと、新しい物語は書けない。脚本家もなかなか大変な仕事である。俳優業は10代からスタートできる。が、脚本は30前後まで努力しないとスタートできない仕事なのだろう。だからといって、年取るまで出来るという保証もなく。依頼がなくなれば失業。女優業も厳しいが、脚本家の仕事も過酷である。

2014年08月28日 Posted by クロエ at 10:47 │Comments(0) │監督日記
「向日葵の丘」女優業。本当に過酷で厳しい職業。

ある大手俳優プロダクションでは売れていない女優は22歳でクビだという。酷い話に思えるが、ふと考えると正解だと感じた。世間では「22歳なんてまだひよっこ。まだまだ、これから!」と思うだろうが、女優の世界は確かに22歳がボーダーラインだ。
自身の映画を振り返るとき、まさにそれが言える。僕の作品は女子高生がメインである。ということは13〜18歳くらいまで。毎回、オーディションをする。19歳でもギリギリOKだが、20歳以上は募集しない。高校を卒業して1年以上たち。特に成人式を迎えてしまうと、もう女子高生には戻れない。制服を着るとどこか怪しく感じる。それでもアイドルならいい!という映画もあるが、僕は基本、現役高校生しか選ばない。
オーディションで選んだ子たち。撮影で奮闘して、輝く子がいる。そんな子たちとはぜひ次も仕事をしたいが、次回作が3年後、4年後となると、すでに20歳を超えてしまい出てもらえなくなる。そこで主人公のお姉さん役とかを考えるのだが、それでは彼女たちの持つ力を十分に発揮できない。
さらに20歳を超えて、25歳とか30歳とかなると、もうホント役がない。学校の先生とか、近所のお姉さん。主人公のお姉さんには歳が行き過ぎ、お母さんには若すぎ。これが男性だと、新人刑事とか、記者とか、教師、いろんな重要な役があるが、女性の役は非常に少ない。
そう考えてみると、20歳を超えた女優は本当に大変。高校生までなら、学園もの、青春ものというドラマがあるが、それを超えると需要がないのだ。だから、大手プロダクションのいう22歳というのは実はとても正解な年齢。それまでに売れれば、主役のOL、女教師、女刑事、女弁護士というような役もあるが、それ以外だと、ほんと小さな役しか存在しない。
男性なら30超えてからブレイクということがありえるが、女性はまずない。それは実力とかキャリア以前に、役がないということだ。もちろん、レギュラーでなくても、小さな役でも、それらを演じるのは大変なことだし。そんな役柄を演じてくれる女優さがいなければ映画もドラマも成立しない。
ただ、僕が「この女優さんいいな。また、ぜひ、出演してほしい」と思っても、20歳を超えると高校生役は無理になるし。22歳以上の役は物語で2つ3つあるかどうかだ。だから呼ぶことができない。ある有名な女優さん。ある時期、主役をバンバン演じていた。人気も凄い。でも、30代になると仕事がなくなり、10年近く映画にもテレビにも出なかった。
それが最近はまたテレビでよく見かける。お母さん役ができる歳になったからだ。けど、そのまま消えて行く人の方が多いのだ。そう考えると、22歳ころから35歳頃までが女優の厳しい時期。女優は若くしてブレイクし、人気ものになる子が多い。でも、同時に消えて行くのもまた早い。
その意味で22歳にブレイクしていない子が、その先生き延びて行ける可能性は少ない。だから、そのプロダクションは22歳で売れてなければ契約更新をしないのだ。ある意味で「優しさ」といえる。
ただ、可愛いだけでも、演技力があるだけでも生き残れない。見た目だけで、憧れたり、バカにしたりする人もいるが、女優業は本当に過酷で大変な仕事なのである。

2014年08月28日 Posted by クロエ at 10:44 │Comments(0) │監督日記
「向日葵の丘」監督日記 いよいよ、残り1分、、、

1分、60秒、1800フレーム。「あと少し、そのくらい切れるでしょう?」 と思うかもしれない。が、減量に挑んだことのある方なら痛感していると思うが、ある程度の体重を下回ると、なかなか減らないのだ。つまり、あとは骨とか内蔵とか、そんなレベルになってしまう。
映画であと1分というのも、そういう状態だ。1シーンまるまる切れるのはもうない。1秒ずつ、60カ所切れば、1分だが、3秒のカットを2秒にすると意味が違ってくるので、切ることはできない。
それでも探して、30秒ほど、切る。と、まだ手直ししていないシーン。アフレコで台詞を変える予定の場面を直していないことに気づき作業。計ると、また1分に戻っていた。。。
とにかく、もう一度書き出しをして、テレビ画面で確認だ。けど、そのために3時間。かかるのが憂鬱。。。データを全てコピーしておいて、2台のパソコンで編集すれば、書き出し待ち時間の間に、もう1台で編集できたのに。。。
でも、今からコピーすると30時間くらいかかる。。。。
書き出し待ちの間に、CMパートの作業だ。